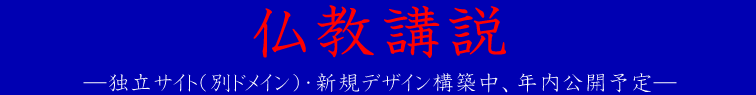
現在の位置
‡ 『雑阿含経』(安般念の修習)
本文13ページ中3ページ目を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
原文 |
訓読文 |
現代語訳
1.原文
『雑阿含経』 (No.803)
宋天竺三藏 求那跋陀羅 譯
如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。修習安那般那念。若比丘修習安那般那念。多修習者。得身心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想修習滿足。何等爲修習安那般那念。多修習已。身心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想。修習滿足。是比丘。若依聚落城邑止住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。善護其身。守諸根門。善繋心住。乞食已還住處。擧衣鉢洗足已。或入林中閑房樹下。或空露地。端身正坐。繋念面前。斷世貪愛。離欲清淨。瞋恚睡眠掉悔疑斷。度諸疑惑。於諸善法。心得決定。遠離五蓋煩惱於心令慧力羸爲障礙分不趣涅槃。念於内息繋念善學。念於外息繋念善學。息長息短覺知一切身入息。於一切身入息善學覺知一切身出息。於一切身出息善學覺知一切身行息入息。於一切身行息入息善學覺知一切身行息出息。於一心身行息出息善學覺知喜覺知樂覺知身行。覺知心行息入息。於覺知心行息入息善學覺知心行息出息。於覺知心行息出息。善學覺知心覺知心悦覺知心定。覺知心解脱入息。於覺知心解脱入息善學覺知心解脱出息。於覺知心解脱出息善學觀察無常。觀察斷。觀察無欲。觀察滅入息。於觀察滅入息善學。觀察滅出息。於觀察滅出息善學。是名修安那般那念。身止息心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想修習滿足。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
このページのTOPへ / 原文へ / 訓読文へ / 現代語訳へ / 語注へ
2.訓読文
『雑阿含経』 (No.803)
宋天竺三蔵 求那跋陀羅 訳
是の如く我れ聞けり。一時、佛、舍衛國祇樹給孤獨園に住しき。爾の時、世尊、諸の比丘に告げたまはく。安那般那念を修習すべし。若し比丘、安那般那念を修習するに、多く修習せば、身心止息し、有覚・有観、寂滅・純一、明分想の修習滿足す。何等をか安那般那念を修習するに多く修習し已らば、身心止息し、有覚・有觀、寂滅・純一にして、明分想を修習し滿足すと為すや。是の比丘、若し聚楽・城邑に依りて止住し、晨朝*1 に衣*2 を著け鉢*3 を持ち、村に入りて乞食*4 するに、善く其の身を護り、諸根門を守り、善く心を繫けて住し、乞食已て住処に還り、衣鉢を挙げ、洗足し已る。或は林中・閑房・樹下、或は空露地に入て、端身正坐し、面前に繫念す*5 。世の貪愛*6 を断じ、欲を離れ清淨にして、瞋恚*7 ・睡眠*8 ・掉悔*9 ・疑*10 を断じ、諸の疑惑を度して、諸の善法に於て心決定することを得。五蓋煩悩*11 の、心に於て慧力をして羸らしめ、障礙分と為て涅槃*12 に趣かざるを遠離す。内息を念じては、繫念して善く学す。外息を念じては、息の長き・息の短きに繫念して善く学す。一切身*13 を覚知して入息し、一切身において入息するを善く学す。一切身を覚知して出息し、一切身において出息するを善く学す。一切身行息*14 を覚知して入息し、一切身行息において入息するを善く学す。一切身行息を覚知して出息し、一切身行息において*15 出息するを善く学す。 喜*16 を覚知し、楽*17 を覚知し、心行*18 を覚知す。心行息*19 を覚知して入息し、心行息を覚知して入息するを善く学す。心行息を覚知して出息し、心行息を覚知して出息するを善く学す。心*20 を覚知し、心悦*21 を覚知し、心定*22 を覚知す。心解脱*23 を覚知して入息し、心解脱を覚知して入息するを善く学す。心解脱を覚知して出息し、心解脱を覚知して出息するを善く学す。無常*24 を観察し、断*25 を観察し、無欲*26 を観察す。滅*27 を観察して入息し、滅を観察して入息するを善く学す。滅を観察して出息し、滅を観察して出息するを善く学す。是れを名づけて、安那般那念を修して、身止息・心止息し、有覚・有観、寂滅・純一にして、明分想の修習満足とする。佛、此の経を説き已りたまひしに、諸の比丘、佛の所説を聞きて、歓喜奉行しき。
訓読文:沙門覺應
このページのTOPへ / 原文へ / 訓読文へ / 現代語訳へ / 語注へ
3.現代語訳
『雑阿含経』 (No.803)
宋天竺三蔵 求那跋陀羅 訳
このように私は聞いた。ある時、仏陀は舎衛国は祇園精舎に留まっておられた。その時、世尊は告げられた。「比丘たちよ、まさに安那般那念を修すべきである。もし比丘が安那般那念を修習して習熟すれば、身体は止息し、心が止息して、尋あって伺あり、寂滅純一にして、明分想の修習を満足するであろう。何を以て、安那般那念を修習すること久しくなれば、身体は止息し、心が止息して、尋あって伺あり、寂滅純一にして、明分想の修習を満足する、と言うのであろうか。この比丘が、もし村落や市街に住み、晨朝に袈裟をまとって鉄鉢を持ち、村に入って托鉢乞食する時、よくその身の振る舞いを正し、諸々の感覚を制して、心をゆるがせにせず、托鉢を終えて住所に帰り、袈裟と鉄鉢を片付け、足を洗い終わる。あるいは林の中、空屋、樹の下、または空き地に入って身を正して結跏趺坐して、よく気をつける。目の当たりに、世俗の貪愛を断じ、欲を離れ清浄にして、瞋恚・睡眠・掉悔・疑を断じ、諸々の疑惑を離れて、善なる法について確信を得るに至る。五蓋煩悩という、心において智慧の力を弱らせ、涅槃に趣かせない障碍となるものから離れる。入る息を念じ、(息の長いこと・息の短いことに)念を繋げて行ずる。吐く息を念じ、息の長いこと・息の短いことに念を繋げて行ずる。身体全体を覚知しつつ入息し、身体全体(を覚知する)にて入息を行ずる。身体全体を覚知しつつ出息し、身体全体(を覚知する)にて出息することを行ずる。すべての身行が静まっていることを覚知しつつ入息し、すべての身行が静まっていつつ出息することを行ずる。すべての身行が静まっていることを覚知しつつ出息し、すべての身行が静まっていつつ出息することを行ずる。喜を覚知しつつ(入出の息をする)、楽を覚知しつつ(入息の息をする)、心行を覚知(しつつ入息の息を)する。心行が静まっていることを覚知しつつ入息し、心行が静まっていることを覚知しつつ入息することを行ずる。心行が静まっていることを覚知しつつ出息し、心行の静まっていることを覚知しつつ出息することを行ずる。心を覚知しつつ(入出の息をする)、心悦を覚知しつつ(入出の息をする)、心定を覚知(しつつ入出の息をする)する。心解脱を覚知しつつ入息し、心解脱を覚知しつつ入息することを行ずる。心解脱を覚知しつつ出息し、心解脱を覚知しつつ出息することを行ずる。無常を観察しつつ(入出の息をする)、(愛欲の)断を観察しつつ(入出の息をする)、無欲を観察(しつつ入出の息を)する。滅を観察して入息し、滅を観察しつつ入息することを行ずる。滅を観察して出息し、滅を観察しつつ出息することを行ずる。これを、安那般那念を修して、身体は止息し心が止息して、尋あって伺あり、寂滅純一にして、明分想の修習を満足することという」。仏陀がこの経を説き終わられたとき、諸々の比丘は、仏陀の所説を聞いて歓喜した。
現代語訳:沙門覺應
このページのTOPへ / 原文へ / 訓読文へ / 現代語訳へ / 語注へ
4.語注
* 『雑阿含経』第803経…SN. M/A“Ekadhammasutta”に対応する。内容的にもほとんど同様。ただし、冒頭ならびに末尾の「得身心止息。有覺有觀。寂滅純一。明分想修習滿足」に対応する一節は見られない。
- 晨朝[じんじょう]…午前六時頃。現在、仏教が伝わった国で托鉢を日常的に行なっている国は、タイ・ラオス・カンボジア・ビルマにほぼ限らえるが、それらの国々でもビルマ南部のヤンゴンでは、托鉢に出る時が遅く朝八時半から九時が一般的であるのに対し、その他地域では6時半頃、北部のマンダレーでは大変早く朝4時から五時には出ている者がある。マンダレーの場合は僧侶の数が多すぎて、それが同時刻に一斉に出るとマズイということがあるためだという。タイやラオス、カンボジアではおおよそ朝六時から六時半に僧院を出るのが一般的。→本文に戻る
- 衣[ころも]…cīvaraの漢訳語。いわゆる袈裟のこと。袈裟とはkaṣāyaの音写語で、意味は「汚れた色」。仏教の比丘は、三衣といって、原則として三種の袈裟のみを着用することが許されている。
その三種とは、安陀会[あんだえ](antarvāsa)・鬱多羅僧[うったらそう](uttārasaṅga)・僧伽梨[そうぎゃり](samghātī)で、順に下衣・上衣・外衣(重衣)とも呼ばれる。安陀会は腰に巻きつけて着用する、いわば腰巻のようなもので、故に僧院の内と外とを問わず、洗浴時を除いて一日中着ている袈裟。三衣の中でもっとも小さいものではあるが、「三輪を覆うを最小とする」などと言って、腰に巻きつけたときに臍と両膝がすっぽり覆い隠されるのが最小限度の大きさ。鬱多羅僧は、僧院内で誦経・瞑想・経律の学習や僧伽の諸行事にて必ず着用しなければならない袈裟。これは普段、右肩を顕わにするように着用する。これを偏袒右肩という。そして僧伽梨は、たとえば托鉢の際など、僧院・精舎や住居としている森林・洞窟から出て市街や村など集落に出るときに着用しなければならない袈裟。その場合、両肩を覆い隠すよう身体にグルッと巻くようにして着用する。この着用法を通肩という。もしくは、折りたたんでただ左肩に掛けることもされる。僧伽梨は寒い時に防寒着としても用いることが出来るが、そもそも寒さが原因でこの僧伽梨の使用が始まった。鬱多羅僧と僧伽梨の大きさは同じであるが、僧伽梨は必ず二重[ふたえ](裏地がなければならない)に作られなければならないため、これをまた重衣ともいう。これら三衣は、場合によっては着用していなくとも、常に側に携えていなければならない(摂衣界などといって、寺院内・精舎の境内にある場合はその限りでない)。また更に、これにいわば下着として鬱多羅僧の下に着用する左肩を覆う布(僧祇支[そうぎし])が許可され、安陀会の下に着用する腰巻も使用されている。なお、比丘の三衣一鉢という言葉があるが、これは「比丘は三衣一鉢しか所有できない」などという意味ではなく、「三衣一鉢を持っていなければならない」という意味のもので、三衣一鉢を備えていなければ比丘とはなりえない。
本経には、比丘が托鉢から帰って「衣鉢を挙げ(袈裟と鉢を片付け)」という一節があるが、ここで言われる袈裟とはただ僧伽梨のことであって、三衣すべてではない。
インドというおおよそ年間を通して温かい土地では、袈裟そしてそれらの布だけで過ごすことが可能であった(北インド・ガンジス川中流域でも冬季の朝晩はかなり冷えるため、三衣は必要)。しかし、仏教がインド亜大陸に広まり、またチベット、支那・日本などに伝わると、そこでは気候がまるで異なるため三衣だけで過ごすことが非常に困難となった。また、偏袒右肩にする際、直接肌をあらわすことは文化的・社会的にも好ましいことではなかった。そこで支那では、袈裟の下に着る本来下着であった上記のものを支那風・宮廷風に改変したのが褊衫[へんざん]と裙[くん]である。褊衫は僧祇支が元になっているものである。支那以来日本でも、本来ならばどの宗派であっても、方服と言える褊衫・裙と三衣を着用して然るべきものであった。しかしながら、以降それがさらに改変されていき、為にむしろ袈裟がある意味で二次的・儀式用の衣装的ものとなっていった。たとえば褊衫と裙をつなげて簡略化したものが直綴[じきとつ]であり、これは禅僧が考案したものであるという。しかし、直綴となってしまうと律の規定からはズレた、方服とは言えないものとなる。
そして、それらが日本に伝わると、僧侶が朝廷のヒエラルキーの中に組み入れられ、また皇族・貴族たちが出家することが一般的となるなどしたために、衣は官服の様相を呈するようになりさらにあれこれと変えられて色や形の規定がなされ、また袈裟はますます華美なものとなったり簡略化さて、およそ袈裟の本来から遠く離れたものとなっていった。日本の僧侶らの律に関する無知、これを恣意的に無視する態度もこの傾向をどんどんと推し進めていった。しかし、これは非常に面白いことに、支那では現在、律の規定にそった衣として考案された褊衫裙など古い形の物を忘れてしまって伝えていないのに対し、日本(律宗など南都の衆と真言宗)では、あたかも吉原の花魁の衣装の如き高価で華美に過ぎてむしろ下品な袈裟を用いる場合がありながらも、褊衫裙などいまだ当初の形のままに伝え用いている。今から四~五十年前の昔の高野山では、律僧らは褊衫裙に七条を常時着用し、下山する時には直綴を着るなどしていたという。今はただ四度加行の時をはじめとして、各種三昧法や護摩行などの瞑想を修する時だけに着る「お衣装」に過ぎないものとなっている。また、およそ日本仏教で用いられている特に五条袈裟とされるすべての袈裟、譬えば禅宗の掛絡や浄土の威儀細、真言宗の大威儀、略五条・折五条等々はすべて袈裟と名付けられたただの布切れで、袈裟を淵源としたものではあるであろうが、袈裟ではまったくなくなっている。江戸時代中期、このようなのを正そうと大阪の慈雲尊者が奮闘され、袈裟の形から着用法まで往古の形に戻さんと奮起された。明治以来現在にいたるまで、真言宗では慈雲尊者の正された袈裟「如法衣」を用いるようになったが、しかし、その着用法も寸法もまた間違ったものとなってしまっている。そもそも何故に慈雲尊者の改正した袈裟が「如法衣」と呼ばれるかも理解されていない。
東南アジア・南アジアに伝わった分別説部では、仏陀の袈裟をそのままに伝えていると宣伝している者があるがそういうことは全くなく、着用法についても変化して、そのままなどということはありえない。まず、安陀会と鬱多羅僧とは日常的に用いているが、僧伽梨は完全に儀式用のものとなって、ごくごく稀にしか用いない。いや、僧伽梨など、具足戒を受けて比丘となるときに受けただけで、それ以来一度も使ったことがないという者が非常に多い。タイ系の分別説部の僧伽梨など、実用から離れて久しいためか実に小さい、ヘタをすると安陀会よりも小さな布切れとなっている場合がある。それですら箪笥・行李のなかでホコリを被っているようなのが大体である。ビルマでも、たとえば律の厳持なくして禅定無しとするPa Auk[パ・アウ]の門弟など、特に金品に触れない(蓄えない)戒条を厳しく守ろうとしている者らでも、界外においても僧伽梨を常時携帯あるいは着用する者がないのはまったく不思議である。犯戒の罪の重さは全く同一であるのに(その言い訳として、Adhiṭṭhānaしていたならば良いなどと言うけれども、それは僻事であろう)。
今やどこの国においても、 托鉢など外に出るさいに僧伽梨を着用あるいは携帯する者などまず存在せず、すべて上に着用するのは鬱多羅僧のみで済ませている。湿気と暑さの為に外出時に僧伽梨など着用できず、また携帯するのも面倒であることから行われていない。あくまで推測に過ぎないが、東南アジアで行われている鬱多羅僧の通肩の着用法は、むしろ東南アジアのいずこかで考案されたものか。
分別説部の伝わった諸国のうちもっとも律を厳しく守っている国、と世間ではされているビルマでは近年、托鉢時を除き、外出時に袈裟を通肩に着る者がほとんどいなくなってしまっている。やはり「暑いし面倒」というのがその理由である。対して、タイ・ラオス・カンボジアの分別説部などは、外出時には必ず通肩に袈裟を着ているが、偏袒右肩の着用法についてかなり変容(ある意味で装飾的なものと)させている。スリランカは分別説部がインドから最初に伝わった土地で、それを誇ってはいるものの、近世から現代にかけサンガが数度、しかも数百年まったく不在であったり、イギリス統治による混乱があったりしことが原因なのか、そのようなことについての古き習わしの数々をまるで保存していない。現在のスリランカのサンガはすべて、タイとビルマからの輸入したものであって、それぞれタイ式・ビルマ式の行事をまたスリランカ風に変えて行っている。袈裟の着方は非常に長く、引きずるほどに着るのがスリランカの特徴。多数派のタイ系サンガ(Siamopāli nikāya)の者らなど通肩の着方すら全く忘れてしまっており、挙句の果てには通肩に着るのは(自派に比して小さく、貧しく、愚かと卑下する)他派・少数派の者の所行としてむしろ異に思い、見下すにまで至っている。これは袈裟の形や色などについても同様である。→本文に戻る - 鉢[はつ]…pātra(パーリ語はpatta)の音写語、鉢多羅の略。現在、鉢は日本語にもなっているが、もともとはこのようにサンスクリット由来の仏教用語。
比丘が用いて良いのは鉄製(あるいは陶器)の鉢で、石の鉢や木製の鉢は禁止されているから、ここで言う鉢とは鉄鉢[てっぱつ]のこと。仏教の規定からすると、禅宗の徒が用いている漆塗りの木製の鉢や、南方ではビルマで比較的よく用いられている竹製で漆塗りの鉢などは非法。
乞食托鉢を日常的にしなかった為か、托鉢で受けた食事のみをとることを前提としていなかったためか、日本で用いられている鉢は小さすぎて不如法・非法のものが多いようである。『四分律』の規定では、鉢の最大の大きさは三斗(唐代の尺では一斗・日本の尺では四升五合五勺とされる)の米が入り得るもの、最小の大きさは一斗半(唐代の尺では五升)を受け得るものとされる。なお、比丘は玄米であろうと白米であろうと炊いていない穀類を(直接)受けてはならないので、これら米の量はあくまで容量を示すために用いられているもの。
そもそも出家者の鉢とは、その鉢に受けた食だけで一日の量を足らせるだけの容量が無ければならないものであるため、いわば手のひらサイズのものであっては全く用をなさず、故に仏教の鉢とは言えない。→本文に戻る - 乞食[こつじき]…仏教の出家修行者が、午前中にその日の食を乞うて集落の家々をまわること。仏教の正式な出家修行者が生活する上での四大原則の一つ。
比丘は、食べ残しなどを次の日まで保存することが禁じられてるため、病いや外出時などなにか所用が無い限り、原則として常に托鉢をしてその日の食を得なければならないとされる。なんらかの理由で托鉢に出なかった者は、同朋の比丘らとわけあって食べる。
仏教教団が拡大し、僧伽が大僧院などかまえるなどして多くの僧侶がそこに定住するようになった場合、その全員が周囲の集落に托鉢に出て食事を得たり、「托鉢で得た食事のみ」で事を済ましたりするのは非常に難しい。また、故に、僧伽が荘園を所有するなどして、そこからの収入で食事をまかなったということも多くあった。乞食托鉢は、比丘としての生活の四大原則の一つであって、比丘であるならば誰でもすべきことではあるけれども、僧院や精舎の状況・社会全体や僧園周辺の集落の状況などによって、それが不可能であったり常にという訳にいかなかったりなどする場合も多くある。実際、釈尊ご在世当時も、在家信者の食事の招待があった場合、あるいは安居期間中、食の準備が周囲の村人らや大檀越によってなされた場合には、托鉢に行く必要がなかった。なお、寺院内・精舎内での調理は原則禁止されているが、浄地羯磨[じょうちこんま]という、煮炊きする場所だけを結界から除外する過程を経た場所であれば可能。ただし、炊事自体は浄人がするのであって僧侶は炊事してはならない。
例えば仏教の修行法の中には、頭陀行[ずだぎょう]という、比丘が皆すべきものというようなものではなく、厳しい修行生活に身を置きたいという者のみが自主的自律的に長期的恒常的に行う修行項目がある。これに、分別説部は十三支、大乗系は十二支を数える。その中、常行乞食あるいは次第乞食という項目がある。常行乞食とは、他者からの食事の招待を一切受けず、ただ毎日托鉢して得た食だけを食べる行。次第乞食とは、町や村に入って托鉢するとき、(その日の充分な食が得られるまで)「次はこの家、その次はあそこの家」などとあちこちと家を飛ばさずに、その貧富を問わず一軒一軒順に家々を回って托鉢すること。このような行がいわれていることは、ようするにかなり早い段階で、誰もが托鉢をしていたわけでもなかったことを意味する。
ところで、日本の街頭でまれに見られるような、午後に托鉢で町を回るあるいは街角で立つということは、仏教ではありえない。かなりの割合で、街角で一日立って「托鉢のようなこと」をしている彼らは、日本の仏教宗派からすら認められていない似非僧職であるか、浮浪者がその日の酒代などのために僧形をして物乞いをしている、江戸時代に言われたところの願人坊主。→本文に戻る - 端身正座し云々…パーリ経典の対応箇所では‘nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā.’(結跏趺坐し、身体を直くし、面前に念を備える)とある(*以下同様に、パーリ経典の対応箇所を適宜引いていく)。
本経ならびにパーリ経典にもある、この「面前に念を備える」とはいかなることか。多くの論書が面前(parimukha)のmukhaを「上唇・鼻頭」であると解している。mukhaとは口・顔・入り口・正面を意味する語である。安般念を修習する際の念を置く場所として必ず上唇あるいは鼻頭と指定されているのは、このような経説に根拠をもつ。
(しかしmukhaが口の意味であるならば、何故に文字通りの口ではないのか。鼻頭・上唇が良いというならば、口でも良いのではないか、という単純な疑問をもつ者があるかもしれないためにここで言っておく。口を開けたまま集中して長時間安般念の修習など出来ないため口では不可である。これは根拠云々ではなく、経験的事実である。)
坐法に関して、一部の例外を除き、およそすべての経典に説かれるのは、結跏趺坐(あるいは条件付きで半跏坐)に限られている。結跏趺坐でなければならない、などとは言われないが、多くの仏教諸派がおよそ2500年の昔からずっと同じ坐法を伝えてきたことは一考しなければならない。背筋を伸ばして反らし過ぎぬようし、足は安定して股関節ならびに腰をねじらぬようにすること。すると結跏趺坐がもっとも安定した坐法となる(私見では必ずしも結跏趺坐でなくともよく、半跏坐でも良いと思うけれども)。ただ半跏坐は上手く座らなければ股関節ならびに腰に相当な無理が加わるため、坐法を確かなものとしておかなければ長時間坐すことが出来なくなるであろう。
以下まるごと余談となるが、現実問題として、たとえばビルマにおいては半跏坐する者は少なく、結跏趺坐する者などほとんど見られず、両方の足を重ねない胡坐を用いる者が多い。言ってみれば「足を組まない胡座」で、当然左右どちらかの脚を手前として折り曲げた左右の脚がベタッと地に付く。これは足を組まないがゆえに足同士で圧迫し合うことがなく、やや長く坐ることができるが少々安定性にかけ、腰にも負担がかかる。日本の禅宗では(坐布を用いてはいるものの)結跏趺坐にて長時間座り続ける訓練がされている。真言宗ではもっぱら坐布など用いずに半跏坐で行をなし、結跏趺坐する者は極めて稀。それでも半跏坐で普通一刻、長い時は二刻を過ごす。最初はどうやっても痛くてたまらないもので、それがまったく普通であるが、(なかば強制的に)やり続けていくうちにたいしたことではなくなってくる。このような点からも、僧院生活・禅堂生活に身を置いて、ほとんど無理やり身体を適応させていく出家者のほうがずっと有利であることが知られるであろう。実際、仏教のどの派を信仰しているにせよ、在家生活にあってこれをするのは中々難しいことだから、在家の限られた時間の中で瞑想に励もうとする人は、本当に稀有でありがたいことと思う。
たいして修習もせぬ最初から文句ばかりで不合理云々、ニンゲンコーガクの見地から何々と宣うようでは話にならないと思う。根性論を云うのではないけれども、そのうち慣れるものと思って辛抱・忍耐して続けたらいい。やれば出来ることであると信じ、人によって遅速の差が大きくあるとは言え、実際やれば出来ることであるからコツコツやればいい。当たり前の話であるがやらなければ出来ない。太っているならば食を制限して体重を落とし、身体が難いならば柔軟にするのも諸々の利益のあることである。自らを人と比べても詮無いことであるから、誰がどうであるとか気にしてはいけない。→本文に戻る - 貪愛[とんあい]…五欲に対する愛着、欲望。愛欲(kāmacchanda)。→本文に戻る
- 瞋恚[しんに]…怒り。自らの思い通りにいかない時、満たされぬ時に多く放出される、自他を害そうとする強い破壊的感情。瞋(byāpada / vyāpada)。→本文に戻る
- 睡眠[すいめん]…物憂さ。心が晴れやかでなく、ぼんやりと弛緩していること。睡眠(middha)。
パーリ経典ではthinamiddhaと、無気力さを意味する惛沈[こんじん](thina)があって、惛沈・睡眠とセットにして挙げている。ここではただ睡眠とだけあって、無気力さを意味する惛沈[こんじん](thina)が挙げられていないように思われてしまう。『倶舎論』の梵本を参照すると、睡眠と惛沈とはstyāna-middhaとやはり一緒に挙げられている(玄奘三蔵は「惛眠」あるいは「惛沈睡眠」と訳している)。故に一応、ここでの睡眠という語は、thinaを睡としmiddhaを眠としたものと見て良いであろう。→本文に戻る - 掉悔[じょうけ]…掉とは掉挙[じょうこ](auddhatya / uddhacca)で、心がソワソワとして落ち着かないこと。悔はとは悪作[おさ / あくさ](kaukṛtya / kukkucca)で、過去になした善悪の行為を嫌悪・後悔してあれこれ思い悩むこと。→本文に戻る
- 疑[ぎ]…四聖諦・縁起・輪廻(前世・現世・来世)・涅槃について疑い惑うこと。疑(vicikicchā)。→本文に戻る
- 五蓋煩悩[ごがいぼんのう]…先に挙げた貪愛から疑までの五つの煩悩(心所)を五蓋という。パーリ語ではpañca nīvaraṇa(五つの障害)。経文にあるこれに続いての「心に於て、慧力をして羸らしめ障礙分と為て」とは五蓋の説明。
分別説部では、それら五つの心所が心を覆って、様々な善の生じ増上することの障害となることから五蓋というとする。『倶舎論』では、五蓋について「諸煩惱等皆有蓋義。何故如來唯說此五。唯此於五蘊能為勝障故」と説明している。→本文に戻る - 涅槃[ねはん]…「火が吹き消されたこと」(√nir+vā)を原意とする、サンスクリットnirvāṇaの音写語。パーリ語はnibbāna。
仏教における最高最上の平安の境地。すべての煩悩が滅尽し、来世に転生させる因がもはや無くなったこと。そこへの到達が仏教徒の最終目標。ただし、涅槃を説くのは仏教に限らず、仏教に先行するヴェーダ(バラモン教)や仏教と同時期に誕生したジャイナ教でもこれを最上の境地として目標としたが、それへの到達方法やそれをいかに見るかの見解が異なった。
仏教内においても涅槃をいかに見るかで、小乗と大乗では見解が異なる。小乗、たとえば分別説部(上座部)や説一切有部などでは、涅槃を恒常不変の実在するモノ(世界)として見ている。対して大乗では、これを不生不滅の義であるとして、そのような恒常不変の実在であるとの見解を批判して無住処涅槃を説く。→本文に戻る - 一切身[いっさいしん]…身体全体。パーリ経典の対応箇所では、‘sabbakāyappaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati.’(「私は身体の全体を感知し、入息しよう」と彼は学ぶ)とある。ここに言う「一切身」とは、単純に解したならば「身体全体」あるいは「全ての身体」のことに他ならない。しかし、所属部派を異にする論書の多くが、この「身体(kāya)」ということについてそれぞれ異なった解釈をしている。故にこれについては別途の考究が必要。
例えば、Buddhaghosa[ブッダゴーサ]はその著“Visuddhimagga”(『清浄道論』)にて、この一説に解釈を加えている中で、要約すれば「一切身とは息の全体、その息の初めから終わりまで」などと説いている。対して、彼が蹈襲した『解脱道論』では「知一切身我入息如是學者。以二種行知一切身。不愚癡故以事故。問曰。云何無愚癡知一切身。答曰。若坐禪人念安般定。身心喜樂觸成滿。由喜樂觸滿。一切身成不愚癡。問曰。云何以事知一切身。答曰。出入息者。所謂一處住色身。出入息事心心數法名身。此色身名身。此謂一切身」(大正32, P430下段)とする。この『解脱道論』の説の根拠となっているのは、“Paṭisambhidāmagga”, Ānāpānassatikathā(『無礙解道』安那般那念論)にある‘Kathaṃ "sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī"ti sikkhati, "sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī"ti sikkhati? Kāyoti dve kāyā – nāmakāyo ca rūpakāyo ca. Katamo nāmakāyo? Vedanā, saññā, cetanā, phasso, manasikāro, nāmañca nāmakāyo ca, ye ca vuccanti cittasaṅkhārā – ayaṃ nāmakāyo. Katamo rūpakāyo? Cattāro ca mahābhūtā, catunnañca mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ, assāso ca passāso ca, nimittañca upanibandhanā, ye ca vuccanti kāyasaṅkhārā – ayaṃ rūpakāyo.’(どのように「身体の全体を感知し、入息する」と彼は行じ、どのように「身体の全体を感知し、出息する」と彼は行じるのであろうか?身体には二種の身体がある。名身と色身とである。何が名身であろうか?受[感覚]・想[知覚]・思[意思決定]・触[接触]・作為[注意]・名[意識?]・名身[概念?]、これらはまた心行とも呼ばれるが、これらが名身である。何が色身であろうか?四大と四大所造色、入息と出息、相[ニミッタ]と結縛[?]、これらはまた身行とも呼ばれるが、これらが色身である)である。入息と出息すなわち呼吸とは色法であると見なされるのである。『解脱道論』は『無礙解道』の釈に忠実に従っていると見て良い。ブッダゴーサのそれは『無礙解道』の所説を頻繁に引用しつつ、あれこれと詳細に解釈しているものではある。しかし、このように遡ってみると、一切身の解釈については、あえて全面的には従わなかったものと見える。なお、出入息を身体と見るのは、‘Kāyaññatarāhaṃ, ānanda, etaṃ vadāmi yadidaṃ – assāsapassāsaṃ.’(アーナンダよ、――入息と出息、これを名づけて“ある種の身体”であると、私は説く)という、SN. M/Aの“Kimilasutta”ならびに“Paṭhamaānandasutta”の経説に基づく。なお、この説は『雑阿含経』に見られない。
説一切有部の『大毘婆沙論』では「問此觀息風從鼻而入還從鼻出。何故乃說我覺遍身入出息耶。答息念未成觀入出息從鼻入出。息念成已觀身毛孔猶如藕根息風周遍於中入出」(大正27, P136中段)とある。説一切有部では、分別説部がそうするように呼吸と鼻頭との接触を念ずるということを行わない。訶梨跋摩『成実論』にては「遍身者行者信解身虛。則見一切毛孔風行出入」(大正32, P355下段)とあって、これは有部のそれと同様のものであろう。遍身(=一切身)とはいかなるものかの解釈などなされていないが、身が虚ろなものであると了解して風(息)が体中の毛孔より出入していると見るという。とにかくこのように、ここで説かれている身体については種々の解釈が行われている。
ところで、『大毘婆沙論』巻廿六「雜蘊第一中補特伽羅納息第三之四」では、入息出息とは身心のどちらに依って生じるものであるかの議論が長々となされ所説紹介されている。 その冒頭、このような経説を引いている。「謂契經說。佛告長者。此入出息是身法身為本繫屬身依身而轉」(大正27, P132上段)。有部においても入出息を身体とする説を採っていた。→本文に戻る - 一切身行息[いっさいしんぎょうそく]…‘passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī'ti sikkhati.’(「私は身行を止息させて、入息しよう」と彼は学す)とあって、一切に該当する言葉がない。本経にいう一切身行息の「息」とは、passambhayaṃすなわちpassambheti(「止息させる・落ち着かせる」の現在分詞・主格単数)に対応する語であって呼吸のことではない。漢訳では、これを使役動詞として訳されていないようなので、現代語訳ではこれを「静まっている」としておいた。
身行(kāyasaṅkhāra)という語を 単純にそのまま現代的に訳せば「身体の形成力」あるいは「身体という形造られたモノ」となるが、それではまるでしっくりしない。また、上の語注13で挙げた分別説部の『無礙解道』の解釈をそのままここに持ち込むのは不適切のように思う。そこで、ここでは無理に訳さず、身行とそのままにしておいた。
なお、『大毘婆沙論』では「止身行者。謂令息風漸漸微細乃至不生。應知此中念入出息者是總。念短入出息等是別。復次念入出息者是欲界持息念。念短息者是初靜慮。念長息者是第二靜慮。覺遍身者是第三靜慮。止身行者是第四靜慮」と身行を呼吸とし、止身行(身行息)を第四禅であると解している。『成実論』には「除身行者。行者得境界力心安隱故。麁息則滅。爾時行者具身憶處」(大正32, P355下段)と、身行とは麁息であるとしてそれが滅するものとする。「爾時行者具身憶處」とは、経にて一切身行息が身念処に配当されるのに言及したもの。
『解脱道論』では「云何名身行者。此謂出入息。以如是身行。曲申形隨申動踊振搖。如是於身行現令寂滅」と、ここでの身行とはやはり出入息すなわち呼吸であるとしている。呼吸に伴う身体の動きを麁い身行とし、まずこれが止む。そして、これに続けて「復次於麁身行現令寂滅。以細身行修行初禪。從彼以最細修第二禪。從彼最細修行學第三禪。令滅無餘修第四禪」(大正32, P430下段)と、麁なる身体の動きが寂滅したならば、ただ細なる身行すなわち細なる呼吸となって初禅を行じ、最細なる呼吸をもって第二禅、またさらに最細なる呼吸で第三禅を行じ、ついに呼吸は無くなって第四禅を行じるとする。第四禅に至ると呼吸が無くなるというのは経説に基づくもので、それに言及しているもの。この釈からすると、この「一切身行息」以下、行者は呼吸の無い状態で安那般那念を行じていくものとなる。これについて『解脱道論』では、呼吸がなくなってなお出入息を念じるなど不可能ではないのか、という至極もっともな疑義が挙げられ、それについての回答がなされている。この『解脱道論』の所説は、そのまま『清浄道論』において同様に述べられている。いずれにせよ諸部派にて、一切身行息とは畢竟四禅を意味するものとして解されている(禅についての詳細は“禅について”を参照のこと)。→本文に戻る - 一切身行息において…大正蔵経では「於一心身行息」となっているが、一心は一切の誤写であろう。→本文に戻る
- 喜[き]…よろこび、歓喜。‘pītippaṭisaṃvedī...’(「私は歓喜を覚知して…)。
これより以下、諸論における解釈を列挙していく。
『大毘婆沙論』「覺喜者。觀初二靜慮地喜」(大正32, P136中段)。
『成実論』「覺喜者是人從此定法心生大喜。本雖有喜不能如是。爾時名為覺喜」(大正32, P355下段-P356上段)。
『解脱道論』「知喜為事知我入息如是學者。彼念現入息念現出息。於二禪處起喜。彼喜以二行成知。以不愚癡故。以事故。於是坐禪人入定成知喜。不以愚癡以觀故。以對治故。以事故成」(大正32, P430下段-P431上段)。→本文に戻る - 楽[らく]…安らかさ、安楽。楽を分類すれば、身体的なもの(sukkha)と精神的なもの(somanassa)との二種となるが、ここでは身体的なもの。‘sukhappaṭisaṃvedī...’(「私は[身体の]安楽を覚知して…)。
『大毘婆沙論』「覺樂者觀第三靜慮地樂」(大正27, P136中段)
『成実論』「覺樂者從喜生樂。所以者何。若心得喜身則調適。身調適則得猗樂。如經中說。心喜故身猗。身猗則受樂」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「知樂我入息如是學者。彼現念入息現念出息。於三禪處起樂。彼樂以二行成知。以不愚癡故。以事故。如初所說」(大正32, P431上段)。→本文に戻る - 心行[しんぎょう]…大正蔵経では「身行」となっているが、明らかに心行の誤りであるために心行と訂している。先の身行と同じように、ひとまずは心行とそのままにした。‘cittasaṅkhārappaṭisaṃvedī...’(「私は心行を覚知して…)。
『大毘婆沙論』では「覺心行者觀想及思」(大正27, P136中段)とあって、心行とは想と思であるとする。『成実論』では「覺心行者。見喜過患以能生貪故。貪是心行從心起故。以受中生貪故。見受是心行」(大正32, P356上段)として、受を見ることを心行としている。『解脱道論』では「知心行我息入。如是學者說心行。是謂想受」(大正32, P431上段)と心行を想と受であるとしている。→本文に戻る - 心行息[しんぎょうそく]…心の活動が静まっていること。‘passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ...’(「私は、心行を止息させて…)。
『大毘婆沙論』「止心行者謂令心行漸漸微細乃至不生」(大正27, P136中段)
『成実論』「除心行者。行者見從受生貪過。除滅故心則安隱。亦滅除麁受。故說除心行」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「令寂滅心行我息入。如是學者說心行。是謂想受。於麁心行令寂滅。學之如初所說」(大正32, P431上段)。→本文に戻る - 心[しん]…精神作用の主体、こころ。仏教では、心を心の本体と作用とに分けて考えるが、その前者を指す。前者を心王[しんのう]、後者を心所[しんじょ]と言う。‘cittappaṭisaṃvedī...’(「私は心を覚知して…)。
『大毘婆沙論』「覺心者。謂觀識體」(大正27, P136中段)
『成実論』「覺心者行者除受味故。見心寂滅不沒不掉」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「知心我入息如是學者。彼現念入息現念出息。其心入出事以二行成所知。以不愚癡以事故。如初所說」(大正32, P431上段)。→本文に戻る - 心悦[しんえつ]…大いに喜ぶこと、喜悦。満足。‘abhippamodayaṃ cittaṃ...’(「私は心を喜悦させて…)。
『大毘婆沙論』では「令心歡喜等者。佛雖不復令心歡喜攝持解脫。然菩薩時有如是事故復重觀」(大正27, P136中段)と、「令心歡喜等者」と心悦以下心解脱までについてこのように述べている。
『成実論』「是心或時還沒。爾時令喜」(大正32, P356上段)と、先の覚心によって心が沈んだ場合に行うものとしている。
『解脱道論』「令歡喜心我入息。如是學者說令歡喜說喜。於二禪處。以喜令心踊躍。學之如初所說」(大正32, P431上段)。 →本文に戻る - 心定[しんじょう]…集中し、心が統一されていること、三昧。‘samādahaṃ cittaṃ...’(「私は心を統一して…)。
『成実論』は「若心還掉爾時令攝」(大正32, P356上段)と、心が浮ついたときには行うものとする。
『解脱道論』「令教化心我入息。如是學者彼坐禪人。現念入息現念出息。以念以作意。彼心於事令住令專。一心教化以彼心住學之」(大正32, P431上段)。→本文に戻る - 心解脱[しんげだつ]…心から諸々の塵垢(悪しき心の働き・煩悩)を脱すること。‘vimocayaṃ cittaṃ...’(「私は心を解脱させて…)。
『成実論』では「若離二法爾時應捨。故說令心解脫」(大正32, P356上段)、心解脱とは心が沈んでもなく浮ついてもいない状態において為すものとする。
『解脱道論』「令解脫心我入出息如是學者。彼坐禪人。現念入息現念出息。若心遲緩從懈怠令解脫。若心利疾從調令解脫學之。若心高從染令解脫學之。若心下從嗔恚令解脫學之。若心穢污從小煩惱令解脫學之。復次於事若心不著樂。令著學之」(大正32, P431上段)。→本文に戻る - 無常[むじょう]…生滅変化して常住でないこと。‘aniccānupassī...’(私は無常を随観して…)。
『大毘婆沙論』は、まず尊者世友の「隨觀無常者謂觀息風無常」の説を挙げ、さらに他の説として「隨觀無常者觀四大種無常」・「隨觀無常者觀色身無常」・「隨觀無常者觀大種造色等皆是無常」と諸説枚挙し、また大徳の説として「隨觀無常者觀五取蘊無常」(大正27, P136下段)を挙げる。
『成実論』「行者如是心寂定故生無常行」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「常見無常我入息如是學者。彼現念入息現念出息。其入出息及入出息事。心心數法見其生滅學之」(大正32, P431上段)→本文に戻る - 断[だん]…煩悩を断ずること。パーリ経典には、「観察断」に対応する一節が見られない。『大毘婆沙論』ならびに『成実論』の挙げる十六特勝では、ここに対応する箇所に「隨觀斷」・「観随断」としており、全体としてもこの経によく一致している。しかし、『修行道地経』の言う十六特勝では、これに対応する箇所を「若無欲則知」とする。これはむしろパーリ経典の所説に一致し、また全体としてもパーリ経典の所説とほぼ一致している。
『大毘婆沙論』では何を断ずるのであるかということについて、世友尊者説「隨觀斷者觀八結斷」を挙げ、他説「隨觀斷者觀無明結斷」・「觀斷者觀過去結斷」・「隨觀斷者觀苦受斷」を列挙し、大徳説「隨觀斷者觀五取蘊空無我」(大正27, P136下段)とを挙げる。
『成実論』「以無常行断諸煩悩是名断行」(大正32, P356上段)と、単に諸煩悩を断じることとしている。→本文に戻る - 無欲[むよく]…貪欲から離れていること、離欲。‘virāgānupassī...’(私は貪欲から離れていることを観察して…)。
『大毘婆沙論』は世友尊者説「隨觀離者觀愛結斷」、他説「隨觀離者觀愛結斷」・「隨觀離者觀現在結斷」・「隨觀離者觀樂受斷」、大徳説「隨觀離者觀五取蘊苦」(大正27, P136下段)。
『成実論』「煩惱斷故心則厭離。是名離行」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「常見無欲我入息。如是學者。現念入息現念出息。彼無常法彼法無欲。是泥洹入息學之」(大正32, P431上段)→本文に戻る - 滅[めつ]…‘nirodhānupassī...’(私は滅を観察して…)。
『大毘婆沙論』は世友尊者説「隨觀滅者觀結法斷」、他説「隨觀滅者觀餘結斷」・「隨觀滅者觀未來結斷」・「隨觀滅者觀不苦不樂受斷」、大徳説「隨觀滅者觀五取蘊不轉寂滅」(大正27, P136下段)。
『成実論』「以心離故得一切滅。是名滅行」(大正32, P356上段)
『解脱道論』「常見滅我入息。如是學者。彼無常法如實見其過患。彼我滅是泥洹。以寂寂見學之」(P431上段-中段)。
パーリ三蔵の諸経典では、この滅を第十五支とし、第十六支として‘paṭinissaggānupassī assasissāmī'ti sikkhati, paṭinissaggānupassī passasissāmī'ti sikkhati.’(「私は捨離を観察して、入息しよう」と彼は行じる。「私は捨離を観察して、出息しよう」と彼は行じる)を挙げる。『雑阿含経』と相応部との十六特勝の相違する点である。なお、『解脱道論』はパーリの第十六支について「常見出離我入息。如是學者。彼無常法如實見其過患。於彼過患現捨。居止寂滅泥洹。使心安樂學之。如是寂寂如是妙。所謂一切行寂寂。一切煩惱出離。愛滅無欲寂滅泥洹」(大正32, P431中段)と、それは涅槃であるとする。→本文に戻る
脚注:沙門覺應(慧照)
(Annotated by Bhikkhu Ñāṇajoti)
このページのTOPへ / 原文へ / 訓読文へ / 現代語訳へ / 語注へ
本文13ページ中3ページ目を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13
原文 |
訓読文 |
現代語訳
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。




