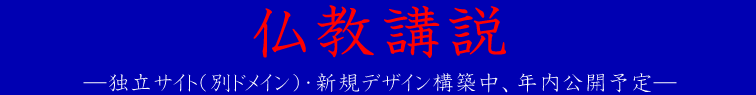
現在の位置
‡ 在家仏教とは何か
在家仏教とは何か | 河口慧海『在家仏教』緒言
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
1.在家仏教?
日本は「在家仏教」?
巷間しばしば、「日本は在家仏教であるから、厳しい戒律を守る必要はない」、あるいは「大乗は在家信者から生まれた仏教であり、ゆえに一般家庭生活を送りながら仏の道をあゆむ在家仏教こそ、真の大乗」、「大乗は在家仏教であり、厳しい戒律を必要としない仏教だ。日本仏教は大乗である。よって我々日本の僧侶はあれこれと細かい戒律を守らなくても良い。戒律を守るのは出家主義・形式主義の小乗」などといった言葉を聞く事があります。
そもそも「在家仏教」とは何でしょうか。
在家仏教という言葉は、かなり曖昧な漠然としたものとして一般に使用されているようで、その実体がいかなるものか把握しがたいようです。そこでまず、一般的な理解がどのようなものか知るための補助として国語辞書を引いてみると、「出家して僧になることなく、俗人の立場で信仰する仏教。また、俗人の信仰の意義を評価する仏教。」(三省堂)とあります。
はたして適切な説明でしょうか。また、このような意味で巷間用いられているのでしょうか。日本では「戒律」というものに対する無理解や誤解が根強いようですが、それらに基づいて形成されたものでしょうか。とすると、いつごろからこれは言われ出したのでしょうか。
結論から言うと、「在家仏教」という言葉そのものや概念は、日本人として初めて数々の危険をおかしてチベットに二度にわたり入国、多数のサンスクリットあるいはチベット語で記された経典を日本にもたらした、河口慧海(1866-1945)が、大正15年(1926)に提唱したものです。
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
2.河口慧海とは
河口慧海

河口慧海は、慶応2年(1866)1月12日、和州堺(現:大阪府堺市)にて、父善吉[ぜんきち]、母常[つね]の長男として生を受けます。幼名は定治朗[さだじろう]。小学校に通っていたが明治10年に退学して家業を手伝い始めるも、夜学に通って漢学を習得しています。
定治朗は21歳から哲学館(現:東洋大学)に通学しています。しかし、明治23年(1890)、定治朗24才のおり黄檗宗の僧として出家。慧海との僧名を得て、東京本所の五百羅漢寺の住職となります。
それから二年後、慧海は、宇治黄檗山万福寺にて、一切経を読破したといいます。しかし、慧海は、僧侶として漢訳経典を読んでいくうち、どうにもそこに説かれていることに疑問を抱くようになります。
漢訳経典の限界
そもそも、日本に伝わり学ばれてきた経典は、サンスクリットなどインドの諸言語から漢語に翻訳されたものです。しかし、そこには言語系統も文化風習もまったく異なるインドと中国では正確に翻訳しがたい点があって意味不明、あるいは翻訳者の解釈などで加筆あるいは削除されてきたものでした。
例えば、仏教の経典には、同じ内容の経典でも、時代などによって翻訳者の異なるものが伝わっている場合があります。そこでそれらを比較してみると、部分的に内容が異なっていることが、しばしばあるのです。有名なものを挙げるならば『法華経』・『華厳経』などです。
また、重要とされてきた経典には、インドや支那の学僧達によってさまざまな解釈・注釈が施された論書が著され、モノによっては絶対の権威あるものとして用いられていました。しかし、それらの中には明確な根拠のない解釈や、語義を敷衍しすぎ、抽象的に過ぎて逆に意味がわからなくなっているものが多数あります。
ゆえに、漢訳経典を直接何度読んでも、いかんとも理解しがたい箇所が出て来るのは必然であり、「権威」に批判的な人がそれら注釈書を用いて読んでも、不審な点が出現するのは当然とも言えるでしょう。
そこで慧海は、サンスクリット原典や、サンスクリット経典を忠実に翻訳するためにつくられたチベット語に翻訳されたチベット語訳経典の入手を志すようになります。時に慧海26歳のことといいます。
それから、慧海師は恐るべき精力をもって旅程計画や語学習得など、その準備に取り掛かります。この期間、師は、慈雲尊者の後継と自負して戒律復興運動を展開していた、真言宗の釈雲照[しゃくうんしょう]の下で戒律について学び、(一般に小乗と言われる仏教の一派)上座部をスリランカに学んで日本で根付かせようと運動していた釈興然[しゃくこうねん]の下にてパーリ語を学んでいます。
秘境チベットへ

そして、明治34年(1901)、ついに慧海は、神戸港を発ってインドに到着。現在からは想像も付かないような困難な道程を踏破し、ネパールを経て、当時実質的に鎖国状態にあったチベット首都ラサに入ります。
そして、日本人であることを伏せつつ、セラ寺というチベットでも名だたる大寺院で約一年間チベット仏教を学び、日本に大量のチベット語経典などを初めてもたらします。
慧海のこの冒険譚は、師によって著された『チベット旅行記』にて読む事ができます。また、慧海は帰国後10年にして再度チベットに入り、チベット語経典とあわせて大量のサンスクリット経典を持ち帰っています。
慧海師は、二度にわたる決死の冒険を成功させたことにより、習得したサンスクリットやチベット語によって、それら言語で書かれた経典を学んで、念願であり目的でもあった数々の不審を明らかにすることが出来ました。
さて、慧海師は日本にて出家した僧侶であり、日本仏教界の堕落しつくした現状は、文字通り「目の当たり」にしています。そして、師はその冒険を通して、インド周辺国の仏教僧の有り様も見ています。これは師の著書における僧侶批判の言辞が生々しく伝える所と言えます。
慧海師は、日本の僧界、チベットの僧界、インドやスリランカの僧界が、それぞれどのようなものかを、文献の中だけでなくその目で確認していた希有の人だったのです。
還俗を決意
慧海師は、チベット語・パーリ語で伝えられてきた律蔵にも目を通しています。漢訳の律蔵はすでに読んでおり、また釈雲照の下で戒律も学んだ事のある慧海師でした。が、チベット語・パーリ語で伝えられた律蔵など諸典籍をさらに読みすすめ、実際に体験した世界各地の僧界のありかたに照らしていくうち、それらはおよそ仏陀が制した僧侶のあり方からは遠く離れたありかたであることに気づいていきます。
それまで慧海師自身は仏教の僧侶、黄檗宗の僧侶の端くれとして自負していたところが、実はまったく非法・不如法の僧侶でしかなかったというのです。いや、僧侶の姿形ばかりで僧侶と呼べるようなシロモノでは無かったと自身を省み、愕然とします。
結果、師は、世界のいかなる場所にも如法如律の僧侶は存在しない、存在し得ないと、「僧侶」そのものに絶望。ひるがえって僧侶として生きていた自身の非法を慚愧し、相当に躊躇したようですが、自身の経験そして信念から、大正19年(1921)もはやこれまでと、ついに還俗を決意するにいたります。
もっとも、師の言からすると、最初から出家のつもりが出家で無かったというのですから、「還俗」という言葉は適切でなく、「似非出家をやめた」「坊さんゴッコをやめた」と言ったほうが良いかもしれません。それは、僧侶という立場に付随する様々な既得権を放棄することを意味しますが、現実問題として、誰人に出来ることではありません。いずれにしろ言動一致の実にいさぎよい行動でした。
しかし、慧海師は還俗後も八斎戒をその生涯において守り遠し、そして菜食(木食)を貫いて、当時のいずれの僧侶などよりも僧侶らしいとさえ言える人生を送られています。
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
3.在家仏教とは
ウパーサカ仏教
河口慧海師が還俗後、はじめて標榜したのが「在家仏教」、あるいは在家をサンスクリットで言った、「ウパーサカ仏教」です。それが具体的にいかなるものかは、その著『在家仏教』にて明らかにしています。
在家仏教とはなにかの要を言えば、「現代を末法であると見て、僧侶と、僧侶が伝えてきた教法に対して絶望し、出家サンガを完全に否定。現在の戒律復興などは不可能で、それを唱えるのは欺瞞であると断定。これらを前提として提唱された、大乗の理念に基づく、純粋に在家信者だけによる信仰をうたったもの」であると言えます。
さらに言うならば、それは「経典は原典を直接学び、既存の宗派の偏向した経典解釈は採らず、いずれの宗派の教義も原則として否定。本尊は釈尊一仏のみ。僧侶のまねごとなどせず、在家者として五戒を厳持し、心を浄化してゆく道」とするものです。
慧海師は、「大乗の徒」であって当然の事ながら「大乗非仏説」などは採っていないものの、これは現代日本における、文献学の成果に基づいてのみ仏教を把握しようとする人々と、ほとんど同様の態度と見ることも出来るでしょう。もっとも、現代の「仏教学信者」ともいうべきそれらの人々とは異なって、慧海師は、生活がまさに仏教に則った、仏教に生きたものです。
前提として「出家者」を全否定
仏・法・僧の三宝は、仏教徒すべてが信仰対象とするものです。しかし、慧海は出家僧侶の集いたるサンガ、つまり一般的な意味での僧宝を全否定しています。そこで、師は、「ウパーサカ僧」なるものを主張しています。
ウパーサカとは、サンスクリットあるいはパーリ語のupāsakaで、「在家の男性信者」を意味する言葉です。「僧」とは、原意を「集まり」とするサンスクリットsaṃgha[サンガ]を漢語に音写した、僧伽[そうぎゃ]を略した言葉です。その漢訳語には「和合」・「衆」などがあります。
さて、サンガとは本来、上に示したように「集まり」を意味する言葉であって、「出家者」を意味するものではありません。しかし、仏教ではサンガと言えば、「出家者の集い」・「出家者の組織」に限定された意味をもつ言葉です。
ちなみに、仏教の出家者は、沙門[しゃもん]あるいは比丘[びく]などと、本来は呼称すべきものです。しかし、支那ではいつしか両者の意味が混同され、出家者をして「僧」あるいは「僧侶」と呼ぶようになっています。そして、日本もこれを踏襲し、僧という言葉でもって、仏教の出家者を指すようになりました。
ウパーサカ僧?
慧海師はこのような点を指摘。僧といっても、それは本来「和合」・「衆」つまり「集まり」の意味であり、その本来の意味で、僧には大きく分けて二種類がある。それは「出家僧(出家者の集い)」と「在家僧(在家信者の集い)」である。しかし、いまや「出家者の集い」は世界のいずこを探しても存在しないが、「在家僧」はある。よって、現代における三宝の僧宝とは、釈尊御在世の当時から存在する「在家信者の集い」であり、これが「ウパーサカ僧」である、としています。
しかしながら、師のこの主張は、現在似たようなことを言っている日蓮系の新興宗教団体もあるようですが、牽強付会の感が否めません。また慧海師は、諸律蔵に基づいても出家者の批判を展開しています。が、師には律がどういったものかの理解が充分ではなく、その批判には、誤解に基づいたいささか極端あるいは滑稽と言えるものが含まれています。
まずそもそも、四衆や七衆という場合の「衆」の原語は、サンスクリットsaṃghaではなく、同じく「集まり」を意味するpariṣad[パリシャッド]の訳語です。これはどうやっても「僧」との訳語を用いえず、よってウパーサカ僧なるものを主張するのは、原語に基づく限り無理があります。
(詳細は”七衆-七つの仏教徒のありかた-”を参照のこと。)
袈裟と僧侶
そして、律についての誤解という点について具体的一例を挙げるならば、慧海師は「三衣を離れて一日一夜を過せば、出家の資格は忽ちに失せるのである」と、当時の僧侶で三衣を常に所持着用している者が一人もいない、という点について批判を展開しています。
三衣とは、人が比丘となるときに必ず揃えていなければならない、三種類の袈裟で、これ以外のものを比丘は着用することができません。その三とは、腰に巻き付ける下衣、常日頃に上半身から下半身までを覆う上衣、僧院や結界から出て村や町に出るときに下衣と上衣の上にまとわなければならない外衣(大衣)のことを言います。
これらは、原則として常に比丘が所持・着用・携帯しなければならないものであると、律蔵において明確に規定されています。これに違反した場合、比丘は他の比丘に対して告白懺悔し、二度と犯さないように努力することを誓わなければなりません。もっとも、比丘が三衣を離れて一日一夜を過ごそうとも一年を過ごそうとも、依然として比丘は比丘で、これによって比丘たる資格を失うことは、律蔵による限り全くありません。
それは比丘としての罪ですが、先に述べたように、律蔵の規定に従って懺悔すれば許されるものであって、僧侶として致命的過失ではありません。極端な例を出せば、たとえ比丘が、俗服に着替えてこっそり外出したとしても、彼は依然として比丘で、これでその資格が消失することはありません。無論それは先に述べたように比丘としての罪であり、また極めて非常識な行為であって、別の観点からサンガによって叱責され、より重い罪が課せられるべきものです。しかし、彼はやはり比丘です。
以上のように慧海師による批判の中には少々極端な説や誤解に基づくものがあるものの、もっともそれは、師が実に苦々しい経験として目の当たりにした、日本仏教界のおそるべき堕落ぶり、そしてスリランカやインドの仏教僧侶のあり方、寺院のあり方など、それは実に醜悪であった事が現代のそれを思えば容易に想像されますが、それらが反映してのことでしょう。
慧海師がやり玉に挙げた、三衣に関して言えば、これは現在でも全世界の僧侶に例外なく言い得ることで、外出時も常に三衣を着用・携帯している者などまずありません。それどころか、正しく袈裟を着ている者すら少なく、三衣を所有してすらいない比丘も多くあります。
世俗のオフィスワーカー、いわゆるサラリーマンでも、どれだけ外が暑かったとしても、仕事時・外出時は常にスーツにネクタイを着用あるいは携帯し、身なりを正しているのに、僧侶はただ「暑苦しい」「面倒くさい」「重い」などの理由で、明文化されている規律を全く無視して、威儀を正さないのは、どう考えてもおかしな話でしょう。しかし、この、いわば怠惰は伝統と化しており、比丘側で問題視する人はまずいません。批判されて当然の、一側面です。
『在家仏教』
慧海師は、『在家仏教』において、日本の各宗派やチベット仏教、経典そのものについてなど、様々なテーマを章立てして批判を展開しています。そして次に、自身の提唱する在家仏教とはなにかを詳細にしています。
『在家仏教』を読めば、現在の漠然と「在家仏教」を言う人たち、あるいは文献学の成果にもとづいてのみ仏教を理解しようとする人々が、師から知らずして影響をうけていることに気づくかもしれません。もっとも、現在巷間でうたわれている「在家仏教」は、慧海師がまったく否定するであろう「ご都合主義 日本教」・「事大主義 -本音と宗教(タテマエ)-」・「観念のお遊戯 浪漫仏教」であると言えるようですが。
在家仏教は、「人間だもの」などと安易な現実肯定を許さず、「仏様がお見守りくださる。すくってくださる」などといった他者による救済を俟つ信仰を容れず、「酒はこの世の習い。少量なら百薬の長。お釈迦様の琴の弦の譬え話のように、厳しすぎてもだらけすぎてもイケナイ。よって、たまになら良いのヂャ」などと、おためごかしを言って飲酒することを正当化しないものです。
在家仏教とは、出家者を容れぬ確固たる信念のもと、後世の者の観念的情意的解釈を廃した仏陀の教えに従い、在家者として最大限持戒した日常生活をおくることを言うものです。
在家における悟りへの道
さて、先に辞書にあった在家仏教の説明は、簡略ながら適切なものと言えるようです。しかし、「在家仏教」なるものの是非はここで論じませんが、世間でしばしば口にされている在家仏教とは、河口慧海が提唱したものとは異なる、ときとしてかけ離れたものとなっていることが知られます。
在家仏教の前提とする所が「僧侶の不在」ですから、現代における祭式執行者としての商業主義的僧侶、鎌倉期からの伝統的呼称でいうと、無戒名字[むかい みょうじ]の比丘が、「大乗(あるいは日本)は在家仏教」などと口に出来るものではありません。
少なくとも「在家仏教」という言葉を口にするならば、一度は提唱者河口慧海師の『在家仏教』を読んで、それがどういう内容のものであるかを知っておく必要があるように思われます。しかし、その分量からして、ここで『在家仏教』のすべてを紹介することは出来ません。また、読みたいと思っても、『在家仏教』などを収録している『河口慧海全集』は発行部数自体が少なく、収蔵している図書館もほとんどないようです(法楽寺が蔵しているこの貴重なる書は、ある人のご厚意による寄進によるものです)。
そこで本書に記される緒言が、その内容を概観するに適したものですから、次項にてその全文を紹介します。これは大正15年刊行の『河口慧海全集Ⅴ』(世界文庫刊行会)所収の『在家仏教』冒頭に記されているものです。
『在家仏教』冒頭を紹介するにあたって、旧漢字・旧仮名遣いは適宜現代のものに改め、難読と思われる漢字にはルビをつけています。
貧道覺應 拝識
(horakuji@gmail.com)
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
在家仏教とは何か | 河口慧海『在家仏教』緒言
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。




