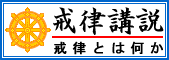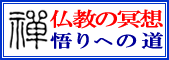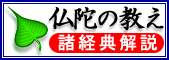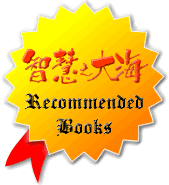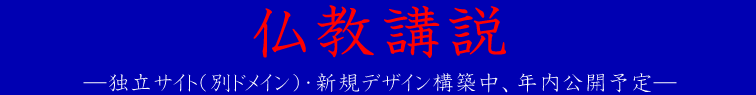
現在の位置
‡ 分別説部(上座部)の心所説 ―仏教における心の分析
分別説部の心所説 | 説一切有部の心所説 | 瑜伽行唯識の心所説
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
1.分別説部が主張する究極的実在
分別説部大寺派
釈尊ご入滅後、幾ばくかの時を経て形成されていった部派仏教(Sectarian Buddhism)と現在呼ばれる仏教諸派の中でも、特にセイロンに展開し、往古にはそこから南インドまで教線を伸ばしていた、分別説部(Vibhajjavādin)という部派があります。この部派は現在一般に、上座部(Theravada[テーラーヴァーダ])と自称し、また通称されています。
(分別説部の成立に関する伝説について触れている項に、“部派仏教 ―セイロン所伝の僧伽分裂説”がある。参照せよ。)
セイロンの伝説では、セイロンに伝わった上座部とは、仏滅後236年の北インド・ガンジス川中流域すなわち仏陀がご活動されていた主な地域から、インドを始めてほぼ統一した大王アショーカ王の王子の一人で比丘のマヒンダという僧によって、直にセイロン島に伝えられたものである。それは、仏滅後100年に僧伽が分裂して誕生した根本の上座部そのものであり、現在にいたってもなおその当時のままを全く伝える純粋無垢の仏教である、などと云われます。
しかし実際は、この上座部と現在通称とされる部派は、おそらく北インドからではなく西インドからセイロン島に伝わって、むしろここで成立・発展したものです。
それがセイロンにて三派に分かれ、それぞれ千年近くもその勢力ならびに王族からの支持獲得をめぐって争っていたうちの一派である大寺派が、いま上座部と呼ばれるもので、現存する部派で唯一のものです。けれども往古のセイロンにおいて、長い間優位に立っていたのは別の無畏山寺派(Abhayagirivihāravāsin)や、分別説部以外の派または大乗の派などであったようです。
しかし、大寺派の僧Sāriputta[サーリプッタ]が、十二世紀末に時の王の支持と後援を取り付けたのを機として、王権の威をもって島内から自派以外を徹底的に排除する大粛清を計ります。その結果、唯一島内に存しえることになったのが、大寺派(Mahāvihāravāsin)でした。その頃、本土たるインドの仏教は、インドへのイスラム教徒の侵入などによってまさに滅びようとしていた時です。
さて、この大寺派の教義の大綱をよくまとめている概論書に、Abhidhammatthasaṅgaha[アビダンマッタサンガハ]というパーリ語で記され、伝えられてきた書があります。
これは、十一世紀のインドの学僧Anuruddha[アヌルッダ]によって著された比較的新しい書ですが、簡にして要を得た非常に優れたものです。いやむしろ、この書によって現在の分別説部大寺派の教学が大成された、とすら言えるもののようです。
以来、分別説部大寺派の教学を知ろうと志す者は誰であれ、まず必ずこの書から学ばなければならないと言える程の必須の入門書となって、分別説部が伝えられてきた国の内では、特にビルマにおいて今も常識的に学ばれています。この書はまた、近現代の日本の文献学者によって『摂阿毘達磨義論』と訳されており、そのように呼称される場合もあります。
分別説部における「無我」の理解 ―人空法有
さて、仏教では、諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・一切皆苦という四つの句を、仏教の仏教たる所以、その教えの核・世界観の要を表す言葉として用いてきました。
この世の一切は「無常」であり、ならば、その故に我々の経験する全ては畢竟「苦」である。であるならば、我々が我・我が物と思っている諸々のモノはどこまでも不如意なる「無我」あるいは「非我」であって、実際それは真であると。しかし、それらを全く真であると知り抜いて、それに則った生活を送った時には、そこに涅槃という、一切の心的苦しみから離れた平安なる境地がある。その時には、人は再び生まれ変わって苦を受けることがない、という言葉です。
分別説部では、我々が経験する常識的な存在、個別の人や事物・事象は仮のものであって実在しない、我いわゆる霊魂のような「不滅の私」・「永遠なる個我」(atta)なるものなども存在しない、故に「無我」(anatta)である、と無我を理解。
しかしながら、部派仏教といわれる諸部派がその他なんらかの実在を認めていたように、究極的には四つの範疇に分類されるモノが実在する、という見解を立て、そのような理解に従った教学を構築しています。
現在の分別説部では、そのような究極的実在を、パーリ語でparamattha[パラマッタ]と呼称します。その意味は、parama(第一の・勝れた)+attha(本質)で、漢訳語ではこれを「第一義」あるいは「勝義」などと言います。あるいは、それら究極的実在を、vatthudhamma[ヴァットゥダンマ]などとも呼称します。これはvatthu(拠り所・基礎)+dhamma(存在)で、いわば存在の根拠、要するに実在するモノのことです。
さて、ではその四つとはなんであるか。これを簡潔に表にして示せば、以下のようなものです。
| - | 名目 | 意味 | 法数 |
|---|---|---|---|
| paramattha (第一義) 【72】 |
citta (心) |
こころ。精神活動の主体となるもの。 | 1 |
| cetasika (心所) |
こころの働き。必ずこころと伴って働く作用。 | 52 | |
| rūpa (色) |
もの。物質の本質。物を成立させている構成要素。 | 18 | |
| nibbāna (涅槃) |
渇愛(飽くことなく欲してやまない欲望)から離れ、何ものからも束縛されず自由な実在する世界。 | 1 |
これら四つの範疇に属するいちいちの法はすべて真に実在するのであり、これ以外の実在を認めるのは誤りである、というのが分別説部における見解です。
現在、俗世間では一部に、何を根拠にその様に言うのか知りませんが、「上座部は小乗ではない」・「小乗では無かった」などと主張する一類の人々があります。
しかし、上に見たように、個我は実在しないけれども、しかし何事か真に実在するものが有るという見解を建てている以上は、これを大乗では「人空法有[にんくう ほうう]」などと云うのですが、まさしく大乗から小乗(Hīnayāna)すなわち「不完全な教え」・「劣った教え」と見なされ、称された教え以外の何物でもないことになるようです。
また、現存する諸部派の成立についての伝承や、それらに対する大乗の見解を記した典籍からしても、多く分裂してその見解の是非を競っていた諸部派は、大乗から小乗と呼称されたものです。
であるとしても、しかし、それら部派の教義・教学体系には見るべきもの、学ぶべき有益な事柄が多くあります。実際、大乗の諸学派はそれら部派を小乗と呼びながらも、しかしそれら(特に説一切有部・経量部・大衆部・犢子部など)を学ぶことは必須のものでした。
実際、大乗であろうが小乗であろうが、いずれも仏陀釈尊という清泉より涌出し、連綿と流れ来たったものです。そこから汲む水は、その広狭・浅深こそあれこれを散ずれば、等しく人を、世界を潤わせ涼やかにする有益なものに相違ありません。
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
2.分別説部の心所説一覧表
Abhidhammatthasaṅgaha(『摂阿毘達磨義論』)の心所説
ここでは特に、先に挙げた第一義とされる四つの範疇のうち、五十二法数えられている心所に焦点をあて、これを表にして列挙したものを以下に示します。
この部派の典籍は、過去の支那においてほとんど漢訳されることの無かったものであり、ここで依用するAbhidhammatthasaṅgahaも過去に漢訳などされたことのないものであるため、まずはパーリ語原名を示しています。しかし、それだけでは一般に意味不明で、また非常に不便であるために、[]内に各語に該当する漢訳語を併記しました。
けれども今述べたように、これは過去に漢訳された経験のないものであるため、[]内に示している訳語は、その他の部派などから該当する訳語を借用しているものです。しかし、分別説部にはあって他部派には無い、この部派独特の術語がいくつかあるのですが、その場合は便宜的に『南伝大蔵経』などで使用されているものを、適宜に用いています。
さらに併せて、それぞれ心所の作用、意味内容をも簡潔に記しています。これら心所の一々の名目は、原則として経典にある言葉であるために他部派とほとんど同様ではあるのですが、時として部派によってその心所の定義などが異なり、故に意味内容が相違しています。必ずしも他の部派と同じ内容のものでないことを注意しなければなりません。
| - | 心所の分別 | 心所の名目 | 作用・意味 | |
|---|---|---|---|---|
| cetasika (心所) 【52】 |
aññasamāna cetasika 【13】 |
善・不善など、その心所の性質の異同(aññasamāna)に関せず、それらと同調して生起する心の作用。 | ||
| sabbacitta sādhāraṇa 【7】 |
すべての心の生じるあらゆる場所・瞬間に、共に生起する、心の基本的・根本的作用。 | |||
| phassa (触) |
刺激。感覚器官と対象と認識とが相応して生じる働き。 | |||
| vedanā (受) |
感受・感覚。心身の苦・楽・不苦不楽いずれかを感じる働き。 | |||
| saññā (想) |
表象。感覚した対象の形象、例えば男女など、その差異を知る働き。記憶。 | |||
| cetanā (思) |
意思。表象した対象を知り考える、心の主たる働き。 | |||
| ekaggatā (一境性) |
集中。定めた認識対象から、意識をそらさず集中する働き。 | |||
| jīvitindriya (命根) |
寿命。心と心所を維持・存続する働き。精神活動を支える働き。 | |||
| manasikāra (作意) |
喚起。心を覚醒・揺動させ、感覚する対象に引きつける働き。気づき。 | |||
| pakiṇṇaka 【6】 |
浄心・不善心のいずれにおいても、雑多(pakiṇṇaka)に生起する心の作用。 | |||
| vitakka (尋) |
思考。知覚する対象について、漠然と考える働き。 | |||
| vicāra (伺) |
思惟。知覚する対象について、細かに考える働き。 | |||
| adhimokkha (勝解) |
確認。知覚する対象を、それが何である、と確定する働き。 | |||
| vīriya (勤) |
努力。目的を達成するため挫けず、努めて行為し続けようとす働き。 | |||
| pīti (喜) |
愛好。知覚する対象を、好み喜ぶ働き。 | |||
| chanda (欲) |
意欲。何らか行為しようと求める働き。 | |||
| akusala cetasika 【14】 |
不善(akusala)なる心と倶に生起する作用。むしろ心を不善にする働き。 | |||
| moha (痴) |
愚痴。認識する対象について無知である働き。 | |||
| ahirika (無慚) |
悪を為すことに自ら恥じない働き。 | |||
| anottappa (無愧) |
悪を為すことに他に対して恥じない働き。 | |||
| uddhacca (掉挙) |
躁。心をして騒がしく、落ち着かせない働き。 | |||
| lobha (貪) |
貪欲。知覚する対象に執着し、さらに欲する働き。 | |||
| diṭṭhi (見) |
邪見。ものごとを、真実に反して理解する働き。 | |||
| māna (慢) |
傲慢。心をおごり高ぶらせる働き。 | |||
| dosa (瞋) |
怒り。自・他の人・物事に対して怒る、衝動的働き。 | |||
| issā (嫉) |
嫉妬。他の成功・優勢・徳性・長所などについて、不快を催す働き。 | |||
| macchariya (慳) |
吝嗇。己の保持する財産・法を物惜して、他に施そうとしない働き。 | |||
| kukkucca (悪作) |
過去に為し、又は為さなかった善・悪の行為を追憶し、後悔する働き。 | |||
| thina (惛沈) |
鬱。心身をして鈍重に、沈み、塞ぎ込ませる働き。 | |||
| middha (睡眠) |
心を惚けさせ、不活発にさせて、対象の把握を不明瞭にする働き。 | |||
| vicikicchā (疑) |
疑惑。四聖諦、因縁生起・業果三宝について確信せず、迷う働き。 | |||
| sobhana cetasika 【25】 |
浄らかな(sobhana)心においてこそ生起する作用。必ず常に生起する作用と、そうでないものとがある。 | |||
| sobhana sādhāraṇa cetasika 【19】 |
すべての浄らかな(sobhana)心と倶に、常に生起する作用。 | |||
| saddā (信) |
三宝・因業・輪廻などを信じる働き。 | |||
| sati (念) |
(「善なるもの」を)心に留めて忘れない働き。 | |||
| hirī (慚) |
悪を為すことに、自ら恥じる働き。 | |||
| ottappa (愧) |
悪を為すことに、他に対して恥じる働き。 | |||
| alobha (無貪) |
知覚する対象に執着せず、さらに欲しない働き。 | |||
| adosa (無瞋) |
己の意に反する対象に対しても怒らない働き。 | |||
| tatra- majjhattatā (中捨) |
落ち着き。心と心所の均衡を保つ働き。 | |||
| kāya- passaddhi (身軽安) |
受・想・行蘊の集まり(kāya)即ち心所、また身体を、安らかとする働き。 | |||
| citta- passaddhi (心軽安) |
心(識蘊)を安らかとする働き。 | |||
| kāya- lahutā (身軽快性) |
受・想・行蘊の集まり、即ち心所、また身体を、軽やかとする働き。 | |||
| citta- lahutā (心軽快性) |
心を軽やかとする働き。 | |||
| kāya- mudutā (身柔軟性) |
受・想・行蘊の集まり、即ち心所、また身体を、柔軟とする働き。 | |||
| citta- mudutā (心柔軟性) |
心を柔軟とする働き。 | |||
| kāya- kammaññatā (身適業性) |
受・想・行蘊の集まり、即ち心所、また身体を、滞りなく作用させる働き。 | |||
| citta-kammaññatā (心適業性) |
心を滞りなく作用させる働き。 | |||
| kāya- pāguññatā (身練達性) |
受・想・行蘊の集まり、即ち心所、また身体を、善く練り整わせる働き。 | |||
| citta- pāguññatā (心練達性) |
心を善く練り整わせる働き。 | |||
| kāyujukatā (身端直性) |
受・想・行蘊の集まり、即ち心所、また身体を、正直とする働き。 | |||
| cittujukatā (心端直性) |
心を正直とする働き。 | |||
| virati cetasika 【3】 |
十悪のうち最初の七悪の禁断・抑制(virati)のある心と倶に生起する作用。 | |||
| sammā- vācā (正語) |
妄語・綺語・悪口・両舌の言語に関する四悪を離れ、正しい発言・言葉遣いをさせる働き。 | |||
| sammā- kammanta (正業) |
殺生・偸盗・邪淫の身体によって行われる三悪を離れ、正しい行為・振る舞いをさせる働き。 | |||
| sammā- ājīva (正命) |
身体と言葉の七悪を離れた職業に従事させる働き。職業に関する作用。 | |||
| appamaññā cetasika 【2】 |
その対象とその数を限定しない(appamaññā)心と倶に生起する作用。 | |||
| karuṇā (悲) |
苦しみのうちにある不幸な生命あるものを憐れむ働き。 | |||
| muditā (随喜) |
喜びのうちにある幸福な生命あるものを随喜する働き。 | |||
| paññā cetasika 【1】 |
ただ「識る」のでなく、またただ「知る」のでなく、物事の本質を見通し知り抜く作用。 | |||
| paññindriya (慧根) |
般若。ものごとの真実なる姿、本質を知る働き。 | |||
これら分別説部の心所説は、分別説部の阿毘達磨を学習するものであれば、まず必ず全て記憶して置かなければ、どうしてもならないものです。それにはパーリ語ならびに漢訳語とその意味を完全に記憶し、そして出来るならば英訳語も知っておくのが望ましいでしょう。
それを難しいとか多すぎてとても無理などと、それに取り掛かる前から不平を言う人が多くあります。が、たとえば生活・収入に直接関しない娯楽のこと、たとえば映画や歌、本のタイトル、俳優や歌手、著者の名前などかなり多く記憶することが当たり前に出来ている者であれば、誰でも出来ることです。本当に興味があり、これを知りたいという欲求があるならば、それほど困難なことではないと思われますが、どうでしょうか。
といって、実際のところ、最初はパーリ語の、日本語からすれば奇異な発音、そして漢字一文字などで表される術語に慣れるのに一苦労となるかも知れませんけれども。しかし、やってみれば案外大して難しいことでないことに気づくことでしょう。
小比丘覺應(慧照) 拝識
(By Araññaka bhikkhu Ñāṇajoti)
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
分別説部の心所説 | 説一切有部の心所説 | 瑜伽行唯識の心所説
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。