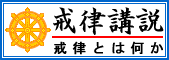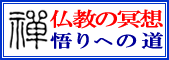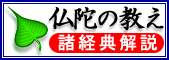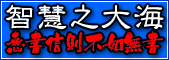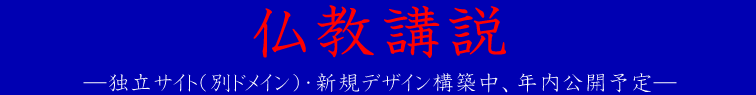
現在の位置
‡ 枝末分裂-部派仏教-
律とは何か |
律の成立 |
律蔵とは何か |
律蔵の成立 |
律の構成
僧伽-比丘達の集い- |
根本分裂 -分裂した僧伽- |
枝末分裂 -部派仏教-
- 目次
- 1.枝末分裂-小乗二十部-
- 2.『異部宗輪論』所伝のサンガ分派
- 3.『舎利弗問経』所伝のサンガ分派
- 4.『善見律毘婆』所伝のサンガ分裂
- 5.スリランカ所伝のサンガ分派
- 6.『ターラナータ仏教史』所伝のサンガ分派
- 7.日本仏教における枝末分裂についての伝統的見解
- ← “戒律講説”へ戻る
- ← “著作権について”
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
1.枝末分裂-小乗二十部-
枝末分裂
仏滅後100年以上を経て、サンガが上座部[じょうざぶ]と大衆部[だいしゅぶ]とに大分裂した根本分裂の後、さらに100年から300年の間に、サンガは最終的に18から20、あるいは24の部派に分かれたと伝えられています。これは今一般に、枝末分裂[しまつぶんれつ]と呼称されています。
これら別れた部派は、特定の「部派そのもの」が一つとして伝わることがなかった中国にて、総じて小乗十八部あるいは小乗二十部と呼称され、日本でもそのように呼び習わしています。
小乗とは、サンスクリットあるいはパーリ語のHīnayāna[ヒーナヤーナ]の漢訳語です。まず、Hīna[ヒーナ]とは、「不十分な」・「~を欠いている」・「劣った」を意味する言葉です。Yāna[ヤーナ]は、「乗り物」を意味します。
小乗は、原意から言うと「不十分な乗り物」あるいは「劣った乗り物」ですが、おおよそ「多くの者を救い得ない教え」「不完全な教え」を意味する言葉として大乗の仏典に頻出する、大乗の立場からのみ用いられる言葉です。
唯一現存する小乗の部派
古来、小乗二十部の一つと言われてきた部派のうち、現存しているのは東南アジア・南アジアに勢力をもつ、上座部と通称される分別説部[ふんべつせつぶ]の末流のみです。最近、「上座部は小乗ではない」という主張をする人々があるようですが、大乗からすれば、これは以下に挙げた諸伝承に基づく伝統説に従っても、現在上座部と言われる部派は、間違いなく小乗諸部の中の一派です。
しかし、世界各国の仏教界がたやすく交流できるようになった今、彼ら部派を特定して「小乗」と呼称するのは控えよう、ということが近年言われています。
よってチベットや日本などではこれを、大乗からすれば小乗と同義語であり、また彼ら分別説部の教学から言っても適切だと言え、また伝統的な呼称である声聞乗[しょうもんじょう]という言葉にて、対外的には呼称するようになっています。また、近年では、仏教学という文献学の世界で、新たに部派もしくは部派仏教(Sectarian Buddhism)なる言葉が作られたことにより、そう呼称することもあります。
現代の一部の人には、東南アジア、南アジアにて信仰されてきた上座部をして、半世紀ほど前に文献学者達が、仏陀在世時代とその直後の時代、そして諸部派が成立した時代などを、学術的にそれぞれ分けて考える必要から創作した、根本仏教あるいは原始仏教、初期仏教などという言葉でもって呼称したがる人もあります。しかし、これはその言葉の定義から言って、全く誤った用法、不適当な呼称で、恣意的に過ぎるものです。
よって今は、古来小乗と呼ばれてきた仏教を、声聞乗あるいは部派、もしくは現在南方で行われているものを特定して言う場合は、ただ上座部あるいは分別説部、南方仏教などと呼称するのが穏当でしょう。
さて、すでに”根本分裂-分裂した僧伽-”にて述べたように、根本分裂と枝末分裂との顛末を伝えている古い典籍は多くなく、今我々が比較的容易に披覧し得るのは、以下に挙げた4、5のものに限られます。すなわち、それぞれ説一切有部、大衆部、セイロンの分別説部大寺派、チベット仏教での伝承を記した典籍です。
それらには、根本分裂の原因を挙げているものはありますが、なぜ枝末分裂が起こったかの原因や経緯を記すものは一部を除いてなく、ただ分裂の系統だけを伝えています。
宗派
古今東西、およそ「派」というものはそうしたもので、得てして不毛なのですが、分裂したそれぞれの部派あるいは宗派は、「我らこそが純粋な仏説を伝えて正しく仏意を解しており正統」と、互いに主張して譲らなかったようです。時には他部派の所説を、「非法」・「非仏説」・「外道」などと激しく批難し、攻撃しています。
現存する書の中に、まさに分裂している過中、あるいはそれ分裂以前に著されたものなどありません。いずれもが分裂が繰り返され、各個が「部派」として成立したかなり後代に、それぞれが著したものです。よって、分裂の経緯を記したそれら書は、当然のことながら自派の正統性を主張すべく記され、伝えられたものです。
つまり、それらはそれぞれの部派が正統であることを証明するために、それぞれの視点・立場から歴史を再構成して記述された書である、ということです。
これに関連して留意すべき点としてあげられるのが、先に述べたことと関連しますが、小乗二十部と言われてきた部派のうち、唯一現存している部派は上座部と自称し、通称されていますが、これを根本分裂のときに別れた上座部と同一視することは出来ず、また実際として同一ではない、という点です。
およそ宗教というものは、伝えられてきたもの、伝えられるものです。どこからともなく、突然降ってわいたように出来上がるようなものではありません。近年は単に、仏教における「保守派」と「革新派」との対立、などという単純な構造によって、サンガの分裂を理解している者が多いようです。しかし、それぞれの派からすれば、自身達が伝える説・解釈こそが仏説、伝統説、正統であり、そうでなくてはいけないでしょう。
革新などと簡単に言いますが、彼らにそのような意識はまるで無かったように思われます。
我らこそが純粋無垢にして正統
現在、上座部あるいはTheravāda[テーラヴァーダ]と通称されている部派には、例に違わず「我らこそが純粋無垢」・「根本分裂以来、きわめて純粋なる伝統説を固持し続けている最も正統な部派」、あるいは過激なのになると「我々と異なる聖典・教義を有する仏教を名乗るものはすべて邪説。あるいは堕落した雑種宗教」云々などと主張する者が、一部見られます。
余談ですが、また現在は、別の観点から「純粋なる仏陀の教え」に迫ろう、信奉しようという者もいます。これは、上座部など部派の教学にも大乗の諸派いずれにも関せず、文献学という科学的学問の成果に基づいてのみ、仏教を理解しようとする人々で、洋の東西を問わず、比較的多くあります。
彼らからすれば、大乗はもとより上座部も夾雑物がタップリ入り込んでいて純粋無垢などでは到底無く、そこで純粋無垢なる仏陀の言葉をそれらから抽出すべく、数々の仏典ならびにそこに並ぶ語句の一々を切り刻むことに勤しんでいます。科学的・学術的に「安心したい」のでしょう。そのようにして絞り出された、純粋なるブッダの教えであれば、初めてこれを確信を持って実行出来る、とまったく真剣に考えているようです。そんなことは無理なのですが。
(関連コンテンツ→”仏教の世界観”)
さて、先に触れたように、古来似たような主張を部派それぞれがしてきたのですが、今や唯一現存する部派にとっては、部派乱立の昔よりずっと言いやすいことでしょう。
しかし実際には、彼らは根本分裂といわれる初めてのサンガ分裂時に成立したとされる上座部とは別物であり、後代にサンガが分裂に分裂を繰り返す中で成立した分別説部、パーリ語でVibhajavāda[ヴィバジャヴァーダ]の末流にある派です。この部派は、また紅衣部あるいは銅鍱部、赤銅鍱部(Tāmraśāṭiya[ターンラシャーティヤ])との異称があります。その原語は、セイロンの都邑の名に由来するものであるといいます。
さらに厳密に言うならば、この部派は、その内部で更に三派に分かれていた事が彼ら自身の伝承ならびにチベットの伝承から知ることが出来ますが、そのうちのMahāvihāra Nikāya[マハーヴィハーラ ニカーヤ](大寺派)という一派の末流です。また、これ以外にも、スリランカや東南アジア諸国では、説一切有部や大衆部、正量部など諸部派ならびに密教など大乗も行われていました。当然、それらの派それぞれが、自派こそ正統との意識を持っていたのでしょうが、結局、最後に王族(統治者)の支持を取り付けて残ったのは、分別説部大寺派でした。これが今言われる上座部の大本です。
一般に、あたかも日本だけが国家仏教などといって、仏教が、国家の庇護や管理の下に制限されて行われてきた特殊なものであったかのように理解し、言う人が多くあります(戦後の左傾教育の残滓でしょう)。が、およそ世界中の仏教の歴史において、いや、これは多くの他の宗教にも該当することでしょうが、国家権力の庇護や理解、あるいは管理なしに、そしてその「功徳」が為政者・国家にもたらされることを期待されずに、繁栄し存続したものなどありません。
仏陀在世の時代もそうであったように、仏滅後の仏教が伝播した区域、インドしかり、チベットしかり、スリランカしかり、東南アジア諸国・中国・日本しかり。それぞれ同様に栄枯盛衰を見ながらも、やはり時々の権力者・国家に守られた者、許容されたもののみが、最終的に後代に生きながらえ繁栄しています。
不毛
今伝わっている数少ない伝承それぞれを比較しても、一致する点と不一致の点とが混在しており、多くの学者があれこれと推論を立ててはいますが、それらによっては、いずれの説が正しいかはもはや不明です。遠い過去に、一味和合を旨とするはずのサンガは、なんらかの理由によって四分五裂。おのおの異なる伝承を残し、その断片を我々は知ることができます。
それらの説に齟齬があったとしても、それらいずれもが、「サンガの伝承」であったことに変わりありません。今は「我らこそが純粋無垢にして正統」などという不毛な主張を対外的にすることなく、それぞれの伝承を、その枠内で伝えれば良いでしょう。
我法真実餘法妄語。我法第一餘法不実。是爲闘諍本。
我が法は真実にして、余法は妄語なり、我が法は第一にして、余法は不実なりとする、是を闘諍の本と為す。
龍樹『大智度論』巻一(大正25, P64上段)
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
2.『異部宗輪論』所伝のサンガ分派
説一切有部が伝える部派分裂
『異部宗輪論[いぶしゅうりんろん]』とは、説一切有部[せついっさいうぶ]の比丘、世友(Vasumitra[ヴァスミトラ])によって、1-2世紀頃に著されたと思われる書です。仏滅後のサンガが分裂してさまざまな部派を形成した経緯と、それぞれの部派の教義の要を、説一切有部の立場から記されています。
著者のヴァスミトラについてはよくわかっていません。ただ、インドから帰国した玄奘三蔵の直弟子であり、この書の注釈書『異部宗輪論述記』を著した法相宗開祖の基[き](一般に窺基[きき]と通称される)は、師からその伝承を聴いていたのでしょう、仏滅後四百年に出生した人と伝えています。
この書は、玄奘三蔵によって、唐代(西暦662年)に漢訳されています。先行して漢訳されたもので他に、真諦訳『部執異論[ぶしゅういろん]』があり、これは6世紀中頃に訳されたものです。現在、サンスクリット原典は伝わっていないものの、チベット訳が伝わっています。
大天の五事-説一切有部が伝える根本分裂の原因-
『異部宗輪論』が伝えるところの、仏滅後はじめてサンガが分裂した原因。それは、仏滅後100数年を経て、摩竭陀(Magadha[マガダ])国の無憂(Aśoka[アショーカ])王の治世にて、当時その学徳・行徳の高さを讃えられている大天(Mahādeva[マハーデーヴァ])という名の比丘が唱えた、阿羅漢[あらかん]についての五つの事項であるといいます。これを大天の五事といいます。
阿羅漢とは、サンスクリットArhant[アルハント]あるいはパーリ語Arahatta[アラハッタ]の音写語で、修行を完成してもはや再び輪廻・再生を繰り返すことのなくなった者、小乗における修行の実質的な最終目標をいう言葉です。
さて、その五事とは何かを、『異部宗輪論』では「餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起 是名真仏教」と大天の頌によって簡潔に伝えています。しかし、これでは簡潔に過ぎて何のことか全く不明です。詳細は、同じく説一切有部の論蔵の一つ『発智論』の注釈書、『阿毘達磨大毘婆沙論[あびだるまだいびばしゃろん]』(『婆沙論』)にあり、これを参照して記せば以下のようなものとなります。
| No | 五事 | 内容 |
|---|---|---|
| 01 | 餘所誘 | 阿羅漢でも、天魔の仕業によって夢精することがある。 |
| 02 | 無知 | 阿羅漢にも、世間的な事柄に関する無知はある。 |
| 03 | 猶豫 | 阿羅漢にも、いまだ心に疑惑がある。 |
| 04 | 他令入 | 阿羅漢には、自らでは阿羅漢となった事を認識できぬ者がある。 |
| 05 | 道因聲故起 | 「苦しい」「苦なり」と口に出すことによって、全き悟りを得る。 |
これらの五つの点について、大天は「真の仏教である」と主張したことが知られます。
そもそも、大天がなぜこのような五事を言ったのきっかけは、大天がある日、おぼえず夢精してしまい、弟子にその衣を洗濯させたときに、弟子からの質問に答えたことに始まったといいます。すでに触れたように、大天は当代きっての高僧として世間に認められ、みずからを阿羅漢であると称していました。しかし律蔵では、人が夢精するのは、その者が心を安立していない為、念を失している為であるとしています。故に阿羅漢であれば、夢精などするはずのないものです。
そこで弟子は、「阿羅漢はすべての煩悩を滅しているはずですが、なぜ阿羅漢のあなたが夢精などするのですか?」という、素朴な疑問を発したのでした。
『婆沙論』の所伝によれば、大天のこの説は、そのようなやりとりの中で弟子への答えとして出されたものです。しかし、大天は、この説を「餘所誘無知 猶豫他令入 道因聲故起 是名真仏教」という偈頌としてまとめ、布薩の場で公然と主張したと言います。これが大問題となったのでしょう。サンガではこれをどうみるかで意見が分かれ、ついにサンガが分裂するに至ったといいます。
二人の大天
もっとも、『異部宗輪論』では、根本分裂の原因を「大天の五事」とするだけで、その経緯の詳細は伝えていません。説一切有部は、この大天の説を悪見つまり邪説であるとし、大天に反する立場を採っていた事が知られますので、大天の説を支持したの比丘達が、大衆部を形成したということになります。
また『異部宗輪論』では、仏滅後二百年が過ぎた頃、同じく大天という名の外道を信奉していた者が、大衆部にて出家受戒し、制多山(Caityaśaila[チャイトヤシャイラ])にあって修行に励んでいたが、やがて先の大天と同じく「五事」を提唱。これによって、大衆部からさらに三つの部派が形成されたとも伝えています(チベットの伝承では、二度目に五事を提唱したのは、大天ではなく「大天の支持者」。また、『部執異論』では、三部ではなく二部が別れたとし、しかし数としては大天による一つの部派として数えています)。
二十の部派
いずれにせよ、大衆部は、仏滅後百年から三百年までの間に分裂を繰り返して、計九の部派を形成(『部執異論』では七)。対して上座部は、仏滅後二百年を過ぎる頃までは結束をたもっていたものの、些細なことから分裂。やがて分裂に分裂を繰り返し、仏滅後三百年を過ぎる頃までに計十一の部派を形成。
ここにサンガは、最終的に上座部系と大衆部系で合わせて二十(『部執異論』では十八)の部派を形成したといい、これが玄奘訳『異部宗輪論』が伝える、説一切有部のサンガ分派説です。
『異部宗輪論』・『部執異論』に依る部派分裂の系統図
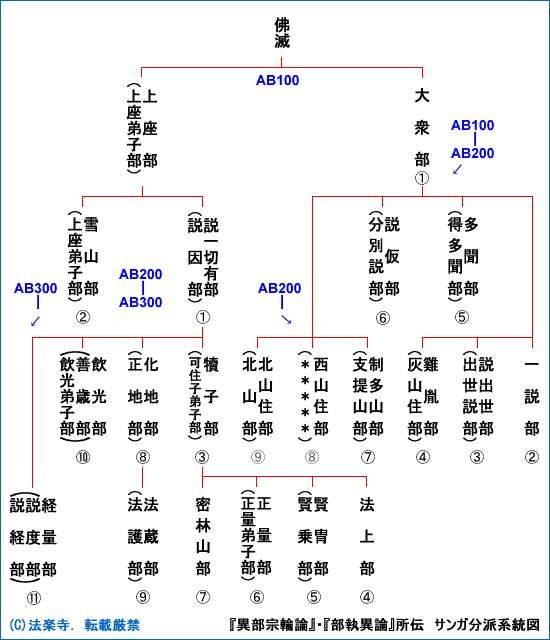
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
3.『舎利弗問経』所伝のサンガ分派
ブッダの予言
『舍利弗問経[しゃりほつもんきょう]』とは、ブッダが入滅される以前、王舎城(Rājagṛha[ラージャグリハ])において、その経題が示しているように舎利弗(Śāriputra[シャーリプトラ])尊者からの様々な質問に仏陀釈尊が答えられるという内容の、比較的短い経典です。中国東晋代に漢訳されたといいますが失訳であって、訳者は不明です。
『舎利弗問経』には、具体的に仏滅後の年数を挙げ、サンガが分裂して様々な部派を形成する様と、それらの部派が着す袈裟の色や特に優れた点などの特徴を、「予言」している一説があります。比較的漢訳された年代が早かったためか、部派の名はほとんど漢訳されず、音写されています(以下に示した系統図では、その他の部派分裂を伝える資料と比較して、おそらく合致するであろう漢訳の部派名を併記)。
『舎利弗問経』では、「摩訶僧祇部。勤学衆経宣講真義。以処本居中。応著黄衣」ならびに「摩訶僧祇其味純正。其餘部中如被添甘露」と説いていることから、摩訶僧祇[まかそうぎ]つまり大衆部[だいしゅぶ]の伝えたものであることが知られます。この経典では、仏滅後にサンガが分裂して諸部派が形成され、その中で大衆部こそが正系であるとしてはいるものの、しかし他部派の存在を排他的に見てはいないことが知られます。
律の規定の改変を主張したのは「上座部」 -大衆部の伝承-
『舎利弗問経』では、ある長老比丘が律について増広することを主張、これがサンガで論争となるも収集がつかず、ある比丘が国王にその裁定を求め、結果としてサンガが分裂すると説かれています。
仲裁を依頼された国王はこれに応じて、旧来の律を護持することを主張する側と、律の改定を求める側とを集めて多数決を行います。結局、旧来の律を護持する側が圧倒的多数で、改定論者は極少数との結果が得られ、そこで王は、旧律も新律のいずれも仏説であるが、それぞれを護持する者達は別々に住することと裁定した、とされています。
ここでは、一般的に「上座部は、仏説である律の厳修を固持した伝統的保守的、長老達の派。大衆部は若い者が主体で、故にその数も多かった革新的な僧達の派」という見方とは、まったく正反対の姿が描かれています。むしろ「律の増広」を主張したのは上座部を形成した者達であったというのです。さらに、ここでもう一つ注目すべき点は、問題となった点が、「律の条項の削減あるいは緩和」ではなく「増広」であるでしょう。仏在世の当時、釈尊の従兄弟であったという悪名名高いDevadatta[デーヴァダッタ](提婆達多[だいばだった])が、「五事」と言って、同じように律を増広してより厳格にすることを提案し、釈尊に拒絶されたことが知られていますが、これと同じようなものであったというのでしょうか。
結果として、旧律の護持を主張した者達は多数であったため摩訶僧祇[まかそうぎ]、新律の護持を主張した者達は少なかったため他俾羅部[たびらぶ]と名づけられたとしています。摩訶僧祇とは、サンスクリットMahāsāṃghika[マハーサーンギカ]の音写語で大衆部[だいしゅぶ]。他俾羅とは、サンスクリットSthavira[スタヴィラ]の音写語で、パーリ語で言うところのThera[テーラ]、つまり上座を指します。
論争の解決法として国王による仲裁のもと採られた多数決は、律蔵に規定されているサンガ内の論争解決法、七滅諍法[しちめつじょうほう]の他人語毘尼[たにんごびに]であると思われます。そして『舎利弗問経』が説いているこの「未来の」出来事は、諸律蔵が伝える、七百人の比丘が毘舍離(Vaiśālī[ヴァイシャーリー])に集って十事を非法とした、今で言う第二結集のことを言っていると見ることも可能でしょう。
さて、これによって得られた結果ならば、サンガとして律蔵の規定に基づく正式なもので、四方サンガとして承認され、ゆえにあらゆる現前サンガが服すべき決定事項です。しかし結局、サンガは分裂。さらに佛滅後二百年から四百年のうちに次々にサンガが分裂していくであろう、と『舎利弗問経』には記されています。
このように、『舎利弗問経』においては、一般的な上座部と大衆部のイメージとはまるで異なる記述が見られます。そしてまた実際のところ、大衆部の律蔵である『摩訶僧祇律』の律の条項数は、他の諸律蔵と比べて最も少ない218ヶ条となっています。
『舎利弗問経』に依る部派分裂の系統図
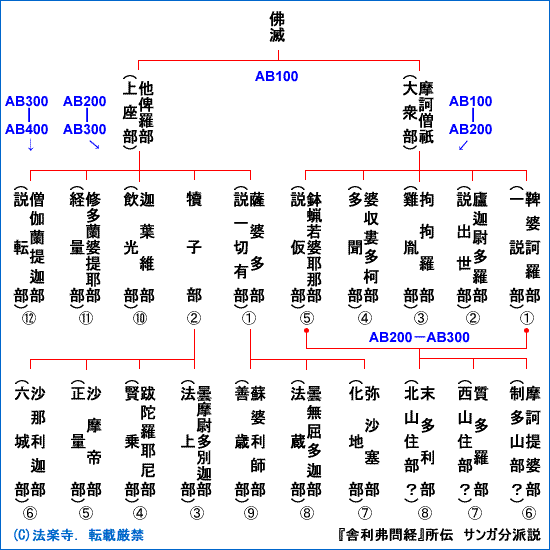
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
4.『善見律毘婆沙』所伝のサンガ分裂
ブッダゴーサによる伝承の記録
準備中
『善見律毘婆沙』(Samantapāsādikā)に見る上座部の開教者と地方
| 派遣された長老の名 | 派遣され開教した国名 | ||
|---|---|---|---|
| 漢語表記 | Pāli語 英字表記 | 漢語表記 (地方) |
Pāli語 英字表記 |
| 末闡提 | Madhyantika マディアンティカ |
罽賓揵陀羅咤国 (西北インド) |
Kaśmīr-Gandhāra カシュミール・ガンダーラ |
| 摩訶提婆 | Mahādeva マハーデーヴァ |
摩醯婆慢陀羅国 (南インド) |
Mahisakamaṇḍala マヒサカマンダラ |
| 勒棄多 | Rakkhita ラッキタ |
婆那婆私国 (南インド) |
Vanavāsi ヴァナヴァーシ |
| 曇無徳 | Yonaka Dhammarakkhita ヨーナカ ダンマラッキタ |
阿波蘭多国 (南インド) |
Aparantaka アパランタカ |
| 摩訶曇無徳 | Mahādhammarakkhita マハーダンマラッキタ |
摩訶勒咤国 (西インド) |
Mahāraṭṭha マハーラッタ |
| 摩訶勒棄多 | Mahārakkhita マハーラッキタ |
臾那世界国 (西北インド) |
Yonakaloka ヨーナカローカ |
| 末示摩 | Majjhima マッジマ |
雪山辺国 (北インド) |
Himavantapadesa ヒマヴァンタパデーサ |
| 迦葉 | Kassapagotta カッサパゴッタ |
||
| 提婆 | Alakadeva アラカデーヴァ |
||
| 帝須 | Dundubhissara ドゥンドゥビッサラ |
||
| 提婆 | Sahadeva サハデーヴァ |
||
| 須那迦那 | Soṇaka ソーナカ |
金地国 (東インド) |
Suvaṇṇabhūmi スヴァンナプーミ |
| 鬱多羅 | Uttara ウッタラ |
||
| 摩哂陀 | Mahinda マヒンダ |
師子国 (セイロン) |
Tambapaṇṇidīpa (Sīhaladīpa) タンバパッニディーパ (シーハラディーパ) |
| 欝地臾 | Iṭṭhiya イッティヤ |
||
| 鬱帝臾 | Uttiya ウッティヤ |
||
| 拔陀多 | Bhaddasāla バッダサーラ |
||
| 参婆樓 | Sambala サンバラ |
||
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
5.スリランカ所伝のサンガ分派
『島史』と『大史』 -セイロンの叙事詩が伝える部派分裂-
現在、東南アジアならびに南アジアに伝わる部派、分別説部大寺派の歴史を伝える書のなかに、スリランカ(セイロン)としては最古の、編年史の体裁をもって綴られた叙事詩『島史』(Dīpavaṃsa[ディーパヴァンサ])があります。この書は、現在上座部と言われる派によって、史書として最も信頼され、依用されている書となっており、その上座部での伝承は、ほとんど全面的にこの書に基づいています。
パーリ語によって記されている『島史』は、紀元4世紀後半から5世紀初頭にかけて作られたもので、作者は不明です。基本的に『島史』は、セイロンの王統が綴られた叙事詩であって、仏教の歴史書などではありません。しかし、その王統の正当性を、「仏教の守護者」に根拠して主張するためでしょう、仏教について多くの項を裂いています。
よって、これは同時にスリランカ仏教の史書として捉えることも出来ます。実際、この書の冒頭から、ブッダの簡略な生涯と、仏滅後の結集ならびに部派の歴史、Asoka[アソーカ]王が仏教に帰依してその息子と伝えられるMahinda[マヒンダ]がセイロンに送られて仏教を伝える経緯などが描かれ、そして初めてセイロンの諸王の事績が綴られて終わっています。
『島史』によれば、ブッダはその在世中に、セイロンに三度飛んでやってきたといいます。
また、この『島史』につづく王統史に、『大史』(Mahāvaṃsa[マハーヴァンサ])があります。これは、『島史』を踏襲して、さらにさまざまな伝説・伝承が加えられ、5世紀末から19世紀初頭までのセイロン史が記されてきた書です。幾世代にもわたり、セイロンの僧侶らによって綴られたものであって、セイロンの分別説部大寺派の立場からの歴史書といえ、相応に脚色されています。
『島史』が記述している時代で、『島史』では一切触れていなかったこと、あるいは軽くしか触れていないことについて、詳細に記述している点などが、特に自派の正当性を主張する下りにて多々見られます。
枝葉分裂について、『島史』と『大史』との伝承によれば、サンガは十八部に別れた後、最終的には二十六部に分裂したといいます。
第二結集 -ヴァッジプッタの十事-
『島史』は、第二結集はまさに仏滅後ちょうど100年、Vesālī[ヴェーサーリー](毘舍離)のVajjiputta[ヴァッジプッタ](跋闍子)が十事を主張したことによって、Kālsoka[カーラーソーカ](訶羅育)王の仲裁のもと行われたとしています。
以下、諸律蔵にはそれが結集であったとの記事など見えず、また全くこのようなことに触れていないので不審な点なのですが、この結果、十事を主張した比丘達は当地のサンガから放逐され、彼らは自身達でまた別の結集を直後に行ったなどと記しています。また、それら放逐された比丘たちは、第一結集にて合誦された律とアビダルマ、ジャータカなどの一部を除いてすべて改変した、と『島史』は伝えています。そして、この時成立したのが大衆部であるといいます。(大衆部の律蔵にも、先に挙げた『舎利弗問経』にもその様な事態があったとの記述、あるいはそれを臭わせるような記述もまったくありません。)
この結集のおり、長老達は、この結集の118年後、Moggaliputta Tissa[モッガリプッタ ティッサ](目犍連子帝須)なる者が現れ、サンガの分裂(教法の破壊)を防ぐこと、Pātaliputta[パータリプッタ](巴連弗:現在のビハール州都Patna[パトナ])にAsoka[アソーカ](阿育)なる王が現れ、全インドを統治すること等、かなりこと細かく「予言」したといいます。
この後、大衆部は次々に分裂し、計六部を形成。対して上座部も大衆部が分裂した後に分裂し、十一部を形成。それぞれが同様に第一結集にて合誦されたものを改変し、ここに正統たる上座部と、不当・非法なる十七部の、計十八部が形成されたと記されています。
これ以降、さらに六部が次第に分裂したといいますが、ただその名を挙げ連ねるだけで、どの部派からどう展開したかは述べられていません。また、より後代に著された『大史』には、セイロンにてさらに二部が分裂したといいます。
第三結集 -アショーカ王の治世-
セイロンの分別説部の所伝と、説一切有部との所伝とで大きく異なる点、それはアショーカ王の即位年代と第三回目に行われたという結集についての伝承です。まず、セイロンの伝承ではアショーカ王は仏滅後218年に即位したというのに対し、説一切有部の伝承では仏滅後116年であるといい、ここにおよそ100年の開きが見られます。
セイロンの伝承では、アショーカ王が即位して8年の仏滅後236年に、再度上座部による結集が行われたといいます。理由は、アショーカ王という強大なパトロンがついて経済的に相当豊かとなった仏教のサンガに対し、民衆の支持を失って貧しくなったジャイナ教など異教の者が、「生活のため」に面従腹背して出家し、これを伝統的には賊住比丘[ぞくじゅうびく]といいますが、ためにサンガが乱れたためであったといいます。この時に行われた結集は、モッガリプッタティッサの主導のもと行われたと伝えられています。
このモッガリプッタティッサに仏教を教授されたのが、セイロンに仏教を伝えたという、アショーカ王の息子Mahinda[マヒンダ]です(7世紀前半にインドを訪れた玄奘三蔵は、マヒンダはアショーカ王の息子ではなく弟であったと聞いたことを、その著『大唐西域記』に伝えています)。
セイロンの分別説部の伝承でここに行われたという結集は、現在一般に第三結集と言われますが、有部の伝承ではこの結集があったことは認められず、サンガとして第三回目の結集はより後代のカニシカ王のもとにて行われたと言い、双方の伝承に食い違いが認められます。また、有部やその他部派の伝承では、アショーカ王が師事した長老は、Moggaliputta TissaではなくUpagupta[ウパグプタ](憂婆麹多)の名を挙げている点も相違している点です。
スリランカ所伝の部派分裂の系統図
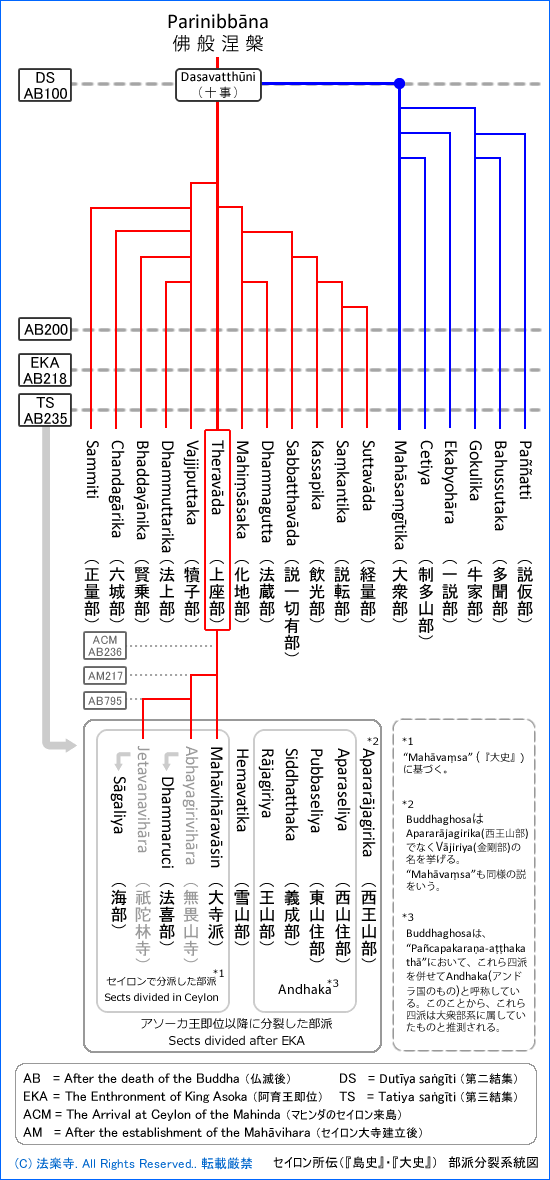
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
6.『ターラナータ仏教史』所伝のサンガ分派
チベット僧ターラナータが記した『インド仏教史』
『ターラナータ仏教史』とは、今もチベットにてよく信頼され用いられている、Tāranātha[ターラナータ]によって著された、インド仏教の歴史書『インド仏教史』の略称です。ターラナータとは、西暦1575年、チベットgtsan[ツァン]に生まれ、17世紀初頭に活躍した、西蔵(チベット)仏教はサキャ派(Saskyapa)の分流ジョナン派(Jonaṇpa)の学僧です。チベット名は、Kundgaḥ sñiṇpo[クンガ・ニンポ]。
ターラナータは、インド巡錫からチベット帰国の後、齢34才のとき、すなわち西暦1608年にこの『インド仏教史』を著しています。彼はこの書を編纂するにあたり、先行する偉大な大学匠Bu ston[プトゥン]など先徳の史書を踏襲した上で、当時のチベットに伝わるインド仏教史に関する典籍、伝承を広く集めています。それはインドのみにとどまらず、チベットへの仏教伝来や、セイロンなど辺境の島へ伝わっていた仏教の状況にも及んでいます。
インドの史書一般と同様、ややその記述内容に混乱が見られるものの、それまでの伝承の誤りを糺すなど示唆に富む内容に溢れています。
さて、ターラナータは、第二結集の時期に関し、チベットに正伝する律蔵(「根本説一切有部律」)には仏滅後110年と説かれており、これを支持しつつ、他部の律蔵には200年、220年に行われたとする説があること、あるインド史にはアショーカ王の没後に行われたとする説があることを紹介しています。
大天の五事
いわゆる根本分裂について。ターラナータは、大天(Mahādeva[マハーデーヴァ])が五事の「非法」を唱えたことにより、ただちにサンガが分裂したとはしていません。
大天は、父母と阿羅漢を殺害(仏教では最悪・極重とされる五つの罪の三つを犯)し、これを隠して比丘となった人であるといいます。もともと聡明であった大天は、出家してたちまち三蔵に通じ、よく禅定をおさめていたため、周囲から阿羅漢と崇められていました。ところがある日、大天が「戒本」(Pratimokṣa-sūtra[プラティモークシャ スートラ]。おそらく布薩の時のこと)を解説するに、「五事」(上記『異部宗輪論』の五事に同じ)を主張。
長老達はこの大天の見解に反対するも、青年比丘達はこれを支持。長老達と大天を支持する青年比丘達は対立し、諍いを起こしたといいます。長老らがこれを否定したのは「経説に反する」ためであったといいます。
サンガ撹乱の張本人 -マハーデーヴァ、バドラ、ナーガセーナ-
そして大天の死後、伝承では悪魔の化身ともいわれる、その支持者であったBhadra[バドラ]という比丘が、また別の五非事を提唱。これによって、さらにサンガに数々の異見が巻き起こって収拾が付かなくなったといいます。これはおそらく、6世紀頃に中観派(自立論証派)の学僧として活躍し、現在もチベットにて偉大な大学僧の一人として讃えられているBhavya[バヴィヤ](清弁[しょうべん])によって著されたNikāyabhedavibhaṅgavyākyāna[ニカーヤベーダヴィバンガヴィヤーキャーナ]の伝承を受けての記述だと思われます。また、この原因として、「異国語」にて経典が説かれるようになったことにより、経典の語法や字義について誤解がされるようになったことも挙げています。
この後、Nanda[ナンダ]王の時代に、Nāga[ナーガ]あるいはNāgasena[ナーガセーナ]という学徳ある比丘が出、また再び「大天の五事」を宣伝してサンガに論争を惹起。これによってサンガは、ついに四部に別れたといいます。この論争の中、Dharmaṣreṣthī[ダルマシュレーシュティー]という阿羅漢が、諍い多く騒がしいサンガを棄て、北部地方に去ったといいます。
ところで、ここに登場する大天の五事を宣伝したという、ナーガあるいはナーガセーナという比丘は、分別説部が伝えるところのMilindapañha[ミリンダパンハ]、あるいは漢訳の『那先比丘経[なせんびくきょう]』に登場する、ナーガセーナ(那先)と同一人物と見てよいでしょう。西北インドに侵入したギリシャの王Menandros[メナンドロス]とナーガセーナとの問答を記したこの書には、ナーガセーナが五事の一部を承認するとおぼしき発言をしていることが認められます。
また、この部派の律蔵の注釈書Samantapāsādikā[サマンタパーサーディカー](漢訳に『善見律毘婆沙』)には、大天をして三達智に到る大徳と讃えていることも見られます(五事を提唱したという大天とおそらく同一人物)。さらに、Dīpavaṃsa[ディーパヴァンサ](『島史』)では、大天はセイロンに仏教を伝えたというマヒンダの出家時の和尚であるとしています。
しかし一方、分別説部が伝えるアビダルマの根本七論書の一つ、Moggaliputta Tissa[モッガリプッタ ティッサ]によって編纂されたなどと伝えられるKathāvattu[カターバットゥ](『論事』)では、説一切有部が非法とした五事を、同じく非法であると断じています。
いずれにせよ、チベットの伝承では、これはすなわち説一切有部、特に根本説一切有部での伝承と言えますが、マハーデーヴァとバドラ、ナーガセーナの三人は、サンガを撹乱し、仏教を乱した張本人と見なされています。
第三結集 -十八部に分裂したサンガ-
さて、この後に出たナーガの追従者たるSthitamati[スティタマティ](堅慧)は、ふたたび大天の五事を強く主張。論争を拡大させたことが、さらに分裂を繰り返すことになったきっかけとなったといいます。すでに四部に分裂していたサンガは、最終的に十八部に分裂したと伝えられています。
四部(根本の四部)に分裂した部派とは、Mahāsāṃghika[マハーサーンギカ](大衆部)・Sarvāstivāda[サルヴァースティヴァーダ](説一切有部)・Vatsiputrīya[ヴァツシプトリーヤ](犢子部)・Haimavatā[ハイマヴァター](雪山部)の四部であるといいます。
サンガでの論争、それはVīrasena[ヴィーラセーナ]王の晩年に始まり、Nanda[ナンダ]王とMahāpadma[マハーパドマ]王の全期、Kaniṣika[カニシカ]王の初期までのおよそ63年間に及んだといいます。カニシカ王の代になり、東方よりPārśva[パールシュヴァ](脇尊者)なる阿羅漢が到来したことにより、この王のもとにて有部の伝承では仏滅後の第三回目のサンガ大会議、第三結集[だいさんけつじゅう]を開催。ついに多年にわたった論争は終結するも、比丘達はそれぞれの見解の相違に基づいて十八のグループを形成し、それらが部派として成立したといいます。
(現在、一般にはセイロンの伝承にあるアショーカ王のもとにて開催された結集を第三結集とし、ここで行われた結集は第四結集[だいよんけつじゅう]と言います。もっとも、ここで説一切有部が行った結集の200年ほど前に、セイロンの上座部の伝承では、セイロンにて第四結集が行われ、経典など仏典が筆写・文字化されたと伝えられています。)
さて、この結集の後、つまりサンガでの大論争の終焉を迎えたことによって、それまで口誦でのみ伝えられてきた律(毘奈耶)が、ここに初めて文字に筆写され、経と論は校訂されて文字化されたといいます。
ちなみに、ターラナータは、この結集以降に、大乗が仏滅後ようやく人間界に流布するに適切な時期となったため、大乗経が世に広まり始めた、と伝えています。
このことから、チベットの伝承では、サンガが論争によってばらばらになる間、つまり仏滅後から諸部派が形成して落ち着くまでの間には、大乗の教えは隠れて世間でまったく流布していなかった、との認識にあることが知られます。
『ターラナータ仏教史』にある部派分裂諸説の系統図
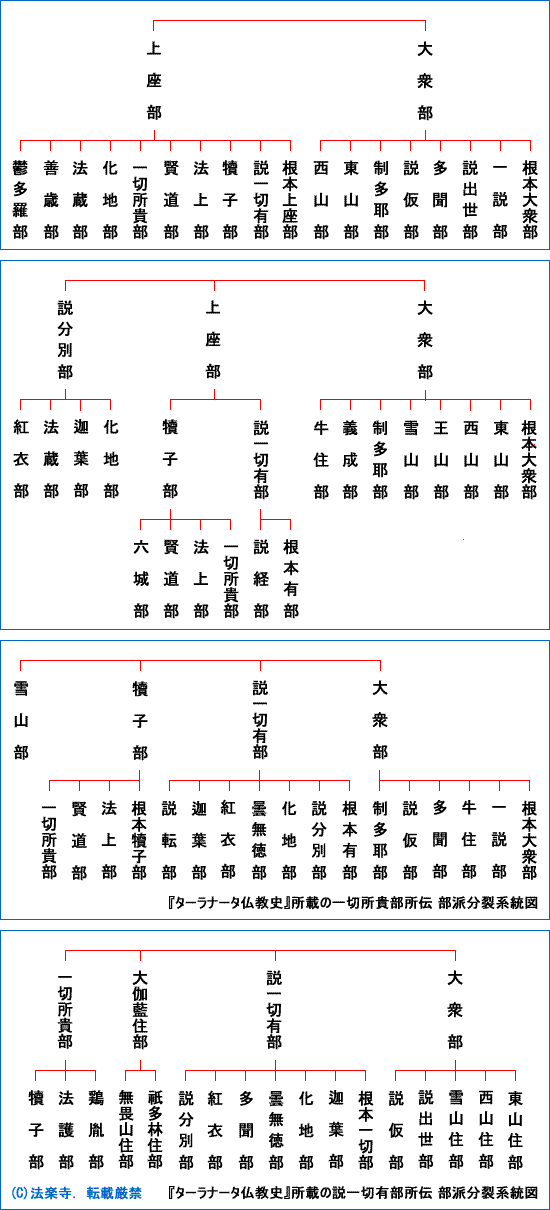
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
7.日本仏教における枝末分裂についての伝統的見解
凝然大徳『八宗綱要』
準備中
金杖の譬え
準備中
沙門 覺應 (horakuji@live.jp)
![]() 前の項を見る
前の項を見る![]()
次の項を見る ![]()
律とは何か |
律の成立 |
律蔵とは何か |
律蔵の成立 |
律の構成
僧伽-比丘達の集い- |
根本分裂 -分裂した僧伽- |
枝末分裂 -部派仏教-
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。